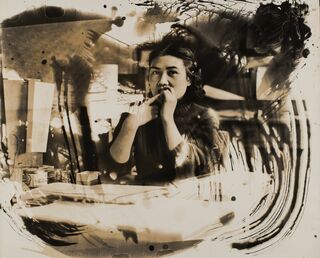気候変動対策を何も行わないと、死亡数の増加が膨らむ可能性が高い(写真はイメージ、Piyaset/Shutterstock.com)
気候変動対策を何も行わないと、死亡数の増加が膨らむ可能性が高い(写真はイメージ、Piyaset/Shutterstock.com)
(篠原 拓也:ニッセイ基礎研究所主席研究員 兼 気候変動リサーチセンター チーフ気候変動アナリスト)
近年、世界的に気候変動問題への注目度が高まっている。地球温暖化の進行により、台風、豪雨、熱波、干ばつ、大規模山林火災、海面水位上昇など、さまざまな影響が地球環境にもたらされている。
 西日本豪雨で広域に浸水し、大きな被害が生じた岡山県倉敷市真備町地区(2018年7月、写真:共同通信社)
西日本豪雨で広域に浸水し、大きな被害が生じた岡山県倉敷市真備町地区(2018年7月、写真:共同通信社)
気候変動問題は、人の生命や健康にも影響を及ぼすとみられている。筆者は、これまで3年以上にわたり、その関係の定量化と、それに基づく今世紀末までの死亡率の予測に取り組んできた。
その結果、このほど「気候変動が激しくなると、死亡数の増加が膨らみ、予測の不確実性が高まる可能性がある」との推論を得ることができた。本稿では、その内容についてポイントを絞って紹介していきたい。
>>【表】気候政策をとらなかった場合、日本の死亡数はどれだけ増えるのか?(予測)
気候変動と死亡率の関係を定式化し、将来の死亡率を予測する
まず、ごく簡単に気候変動と死亡率の将来予測の方法について概観しておきたい。将来予測は、①気候変動の定量化、②気候指数と死亡率の関係の定式化、③将来の気候変動に伴う死亡率の予測の3つのステップを踏んで行った。
①の「気候変動の定量化」では、気温(高温と低温)、降水、乾燥、風、湿度、海面水位といった天気予報でよく目にする項目をもとに気候指数を作成した。1971年から2000年を参照期間として、この期間中のデータの平均値とブレ(標準偏差)を計算しておく。ある月のデータが得られたら、そこから平均値を差し引いて、それをブレで割り算することで、その月の乖離度を計算する。これが気候指数だ。
気候指数が標準正規分布に従うものと想定すると、1を超える確率は約15.9%となる。2を超えるのは珍しいことで、その確率は約2.3%。3を超えるのは大変珍しいことで、約0.1%の確率となる。
気候指数の作成は、日本全国を11の地域に分け、全部で175の観測地点を設定して、過去50年以上の気象データを用いて計算した。その結果、合成指数(高温、降水、湿度、海面水位の4つの指数の平均)は、日本全体で2023年には1.1を上回り、1971年以降の最高水準となった。特に、高温や海面水位の指数は2に近づいており、近年、気候変動が激しさを増していることが数値で示された。
②の「気候指数と死亡率の関係の定式化」では、統計手法の1つである回帰分析を使って、死亡率を①の気候指数(海面水位を除く)を用いた算式で表した。その際、死亡率については、死因を大きく6つに分けたり、男女・年齢群団ごとに分けたりするなど細分化を行い、それぞれに応じて算式を作成した。作成した算式は全部で504本となった。
③の「将来の気候変動に伴う死亡率の予測」では、国内外の5つの気候モデルでの今世紀末までの気象予測データを用いた。各モデルの気象予測データを②の関係式に当てはめることで、気候変動の経路(パターン)ごとの死亡率を予測した。
なお、今回の予測は気候変動と死亡率の相関関係をもとに行った。もし関係があることが示されたとしても、因果関係があるのかどうか、(あるとした場合)どのような因果関係があるのか、までを明らかにすることはできない。このため、以降で述べる結果の解釈については、あくまで筆者の私見であることにご留意いただきたい。