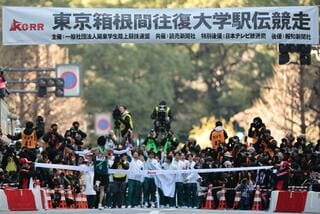ダイエット内科医ががん治療のなぜ?科学的根拠に欠けるがん自費細胞療法が大手を振って提供されるのはなぜか
自家NK細胞療法の重大感染事故に厚労省が緊急命令、科学的根拠欠くがん治療に存在価値はあるのか?
2024.10.31(木)
ここからは、JBpress Premium 限定です。
カンタン登録!続けて記事をお読みください。詳細はこちら
あわせてお読みください

若年層や妊婦も容赦なく襲う高致死率の「人食いバクテリア」、冬場の感染急増に備えるには?
2008年以降に世界拡大した強毒株、A群溶血性レンサ球菌の手強い理由
星 良孝

【10月1日より接種開始】新型コロナ「レプリコン・ワクチン」は本当に大丈夫なのか?ワクチンの第一人者が答える
「5人死亡」「18人死亡」「エクソソーム」「日本だけ承認」……ネットなどの指摘をどう読むか
星 良孝

じわじわ広がる強毒型エムポックス、スウェーデン、タイに続きドイツでも初確認
アフリカでは感染者の3割が性感染と判明、アフリカ・ルワンダでは致死率の高いマールブルク感染症まで発生
星 良孝

内視鏡検査での麻酔を演出に使ったバラエティー番組「KILLAH KUTS」、いったい何が問題なのか?
マイケル・ジャクソンの死亡事故でも使用されたプロポフォール、内視鏡検査の免罪符が許されない理由
星 良孝
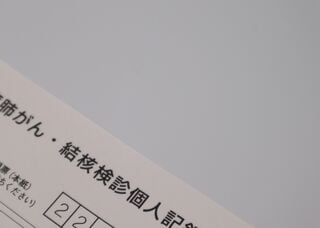
技能実習生や留学生の流入で増える結核の集団感染、育成就労の始動がもたらす結核の2027年問題
フィリピンを中心に複数の薬に耐性を持つ結核も、外国出生者の結核にどう対応すべきか?
星 良孝
本日の新着
明日の医療 バックナンバー

来年開始の医学部定員削減で「地域医療崩壊」に現実味、この課題に医学部受験専門予備校「京都医塾」が取り組む理由
三重 綾子

【アルコールは発がん物質】アルコールの毒は一種類ではない、細胞の「傷つけ役」が体内で次々に増えていく怖さ
齊藤 康弘

【高額療養費制度見直し】「財源に限りが、だから困っている人だけ助ける」では救われない重病・難病患者が続出する
坂元 希美

身体がほとんど動かない重度障害の患者との意思疎通は可能か?微かな動きから読み取る人々と動かない身体が語ること
長野 光 | 西村 ユミ

ワンちゃんネコちゃん向けのAIロボット手術が登場、航空機のパイロットのように獣医師が自動操縦で手術も
星 良孝

エムポックス1bが日本初確認、WHOが緊急事態を解除した直後に走る緊張、今の状況はどうなっている?
星 良孝