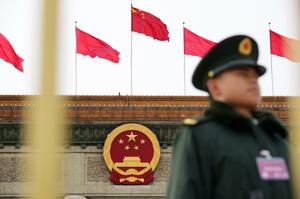言うまでもなく、学校の授業も受験も、またなんとかオリンピックも関係ない。自分で読んだ。
「この正田の書は1ページ21行、121頁の小冊子であるが、ともかくまとまっている。演習問題もある。今日このような簡便で小型な書物もあってよいと思う」(同上)
志村さんは、自主的にマスターし、どうやら演習も自力で解いたであろう正田の書籍にも長短を指摘し、今日、教える必要のない部分ははしょったらいい、と「使える数学」を強調している。
「旧制高校の代数学の教科書には三次方程式や四次方程式の解法が説明されていて、演習問題として次の三次または四次方程式を解けというのが少なくとも十五題以上あったと思う」
「私はひとつも解いた覚えはない、もっとも何次の方程式でも、近似解を求めることはおそらく重要だから、それを簡単に教えるのはよいが、代数的解法にこだわるのは無意味である」
「何でもむかしから教えてきたことを無批判に教えるのは愚劣であるが、鶴亀算や旅人算を教えたように『それを教えることになっている』と中々やめられなかったし、今でもやめられないのである」(「数学をいかに使うか」p.136)
1952年、東京大学理学部数学科を卒業し、直ちに東京大学教養学部で教壇に立ち始めた若き志村青年は、旧態依然たる「使えない」解析幾何などを自主的に廃し、今日では標準的といえる線形代数の講義などに勝手にシフトさせ始めるとともに、20代前半からクロード・シュヴァレー、アンドレ・ヴェイユといった、関連分野で世界の先端を開拓していた当時の第一人者たちと問題意識を共有。
25歳だった1955年9月、そのような環境下で同級の友人谷山豊が発表した「問題」を、谷山氏の不幸な早世後、厳密に定式化して「志村予想」(という表現を、あえてここでは用いたいと思う)に結実。
30余年後、より本質的なこの「志村予想」が解決されることで「フェルマーの最終定理」も結果的に解けてしまった、というのが、実際の流れに近いように思う。