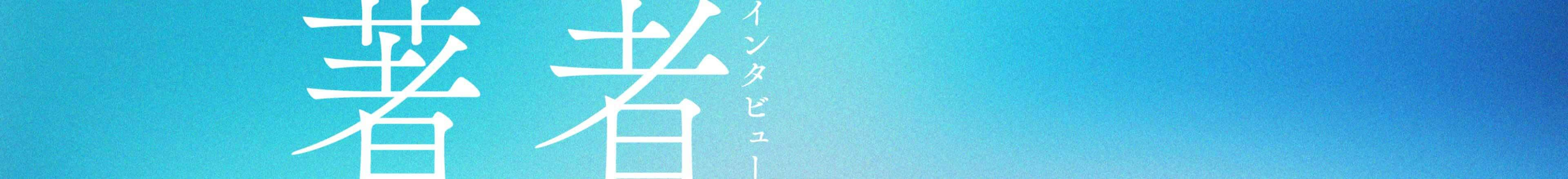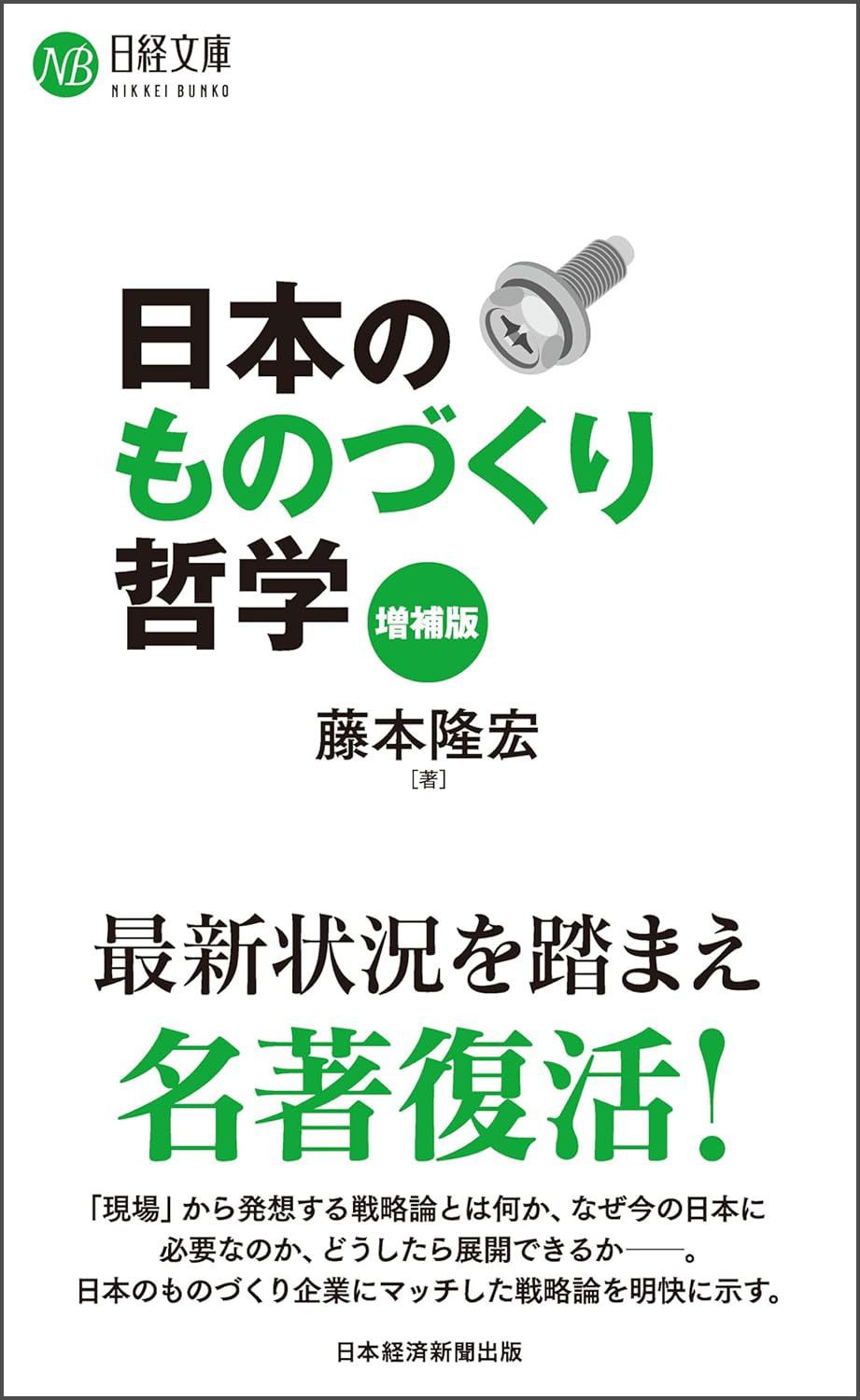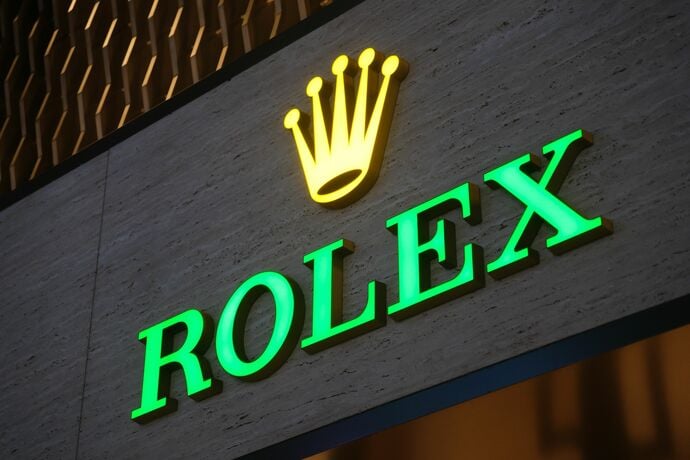出所:共同通信イメージズ
出所:共同通信イメージズ
国内製造業の低迷や衰退を嘆く声がマスコミや経済界の中で聞かれるようになって久しい。しかし早稲田大学研究院教授の藤本隆宏氏は、こうした論調の問題点を指摘する。これまで国内外1000カ所以上の製造現場を分析してきた同氏は、「今の日本に必要なのは、雰囲気で論じる悲観論や楽観論ではなく、産業特性の理解と正しい歴史認識・統計的事実に基づいた“ものづくり現場発の戦略論”だ」と語る。2024年12月、書籍『日本のものづくり哲学(増補版)』(日経BP 日本経済新聞出版)を出版した藤本氏に、日本の製造業に求められる戦略の在り方、トヨタから学ぶべき組織力について話を聞いた。
「日本製造業衰退論」に欠けている「ある視点」
──著書『日本のものづくり哲学(増補版)』では、この十数年、マスコミをはじめとして世の中で語られる国内製造業の悲観論が「建設的な議論を生まなかった」と指摘しています。どのような視点が不足していたのでしょうか。
藤本隆宏氏(以下敬称略) 1990年代以降、マスコミでは日本企業に対する悲観的な診断や受け身の対処法が唱えられてきました。そこに見られた特徴が、短期動向で右往左往する「オーバーリアクション」(過剰反応)です。
とりわけ問題だったのは、自動車、家電、産業機械、金融、ソフトウェアといった産業ごとの組織能力・国際競争力・設計思想などの違いを無視した粗雑な議論の結果、強気一辺倒の「自信過剰」と弱気一辺倒の「自信喪失」の間で右往左往が繰り返されてきたことです。
そして、こうした論調につられてマスコミの論説、政府の施策、企業の戦略なども軸足の定まらない傾向がありました。こうした不安定な論説に欠けていたのは「産業の一般論理」だと考えています。
例えば、マスコミなどで語られる「日本の製造業は衰退した」という声について考えてみましょう。たしかに、日本の製造業の多くは冷戦終結後のグローバルコスト競争の中で約30年、苦戦を強いられ、多くの国内工場が閉鎖されました。しかし、優良工場の存続努力も目覚ましく、生産ラインの物的生産性を数年で数倍にした事例も珍しくありません。
1990年代前半から2020年代前半の約30年間に、国内製造業の就業者数は500万人ほど減少しましたが、付加価値総額は80兆円台から120兆円前後へと増えました。その結果、製造業の付加価値生産性は年間1人当たり約600万円から1100万円超と、約2倍に伸びています。
ところがこの間のマスコミ等の諸論説を見ると、「日本製造業は1980年代が最強、その後は衰退」といった一方的な「日本製造業衰退説」が多く見られます。国の統計や現場の実態を注意深く見れば、その多くが思い込みによる誤認であることがわかります。