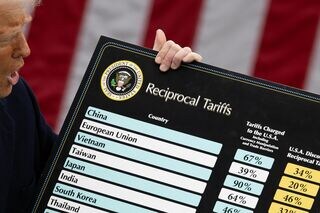石破首相に現役世代の悲鳴は届いているか(写真:代表撮影/ロイター/アフロ)
石破首相に現役世代の悲鳴は届いているか(写真:代表撮影/ロイター/アフロ)
「46.2%」という数字を見て、ピンと来る人はいるでしょうか。財務省が先ごろ発表した国民負担率(2025年度の見通し)です。この数値は「個人や企業が稼いだ所得全体に占める税金・社会保険料の負担割合」を示したもので、近年は5割に迫ろうという水準が継続。物価高と上がらぬ賃金を背景に、「重い負担をなんとかして」という悲鳴にも似た国民の声も増すばかりです。その「国民負担率」をやさしく解説します。
一揆が起きてもおかしくない水準
国民負担率に関する国民の感覚を代弁したかのような国会質疑が今年1月7日、参議院の代表質問で行われました。質問者は浅田均氏(日本維新の会)。本会議場の中央に立ち、浅田氏は次のように迫りました。
「本来は豊かな社会をつくるはずの社会保障制度が、一部の国民にとって過度な負担となり、国の活力をそいでいます。所得に対する社会保険料と税金を合わせた負担割合を表す国民負担率は実に45%を超え、給与の半分を召し上げられている状態です。特に現役世代が過重な負担を負っており、これが若い世代が結婚、子育ての将来展望を描けない要因になっているのは明らかではないでしょうか」
これに対して石破茂首相は、OECD(経済協力開発機構)の加盟36カ国と比較すると、それほど悪い数値ではないと説明。コロナ禍当時と比べても若干低下しているとし、問題ではないとの認識を示しました。
しかし、国民負担率の重さこそ最優先で解決すべきだとの声は国会でも切れ目なく続いています。最近では「五公五民」という語句を使って政府の姿勢をただすケースも増えてきました。例えば、今年2月12日の衆議院内閣委員会で橋本慧悟氏(立憲民主党)は、こう質問しています。
「物価上昇に賃金上昇が追いつかず、国民は手取りのアップ、使えるお金を増やす政策をまさに望んでいると考えています。働いても働いても、税金と社会保険でその収入の約半分を取られてしまって、江戸時代でいうと年貢制度、五公五民です。収穫した米の5割を年貢として納めて、残りの5割が農民の手元に残る。そんな状況で、物価高騰が続き、生活必需品の価格も上がって日々の生活が苦しい。これが国民の切実な声だと思います」
江戸時代の「五公五民」は各藩に納める年貢がいかに重かったかを示す言葉で、百姓一揆の発生と紙一重のラインだったとされています。そんな「五公五民」という語句を使って国民負担率の重さを指摘する国会質問は、令和に入って衆参合わせて21回に及んでいます。