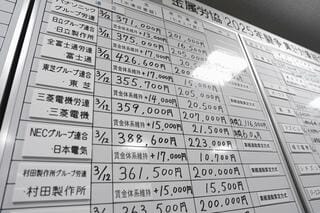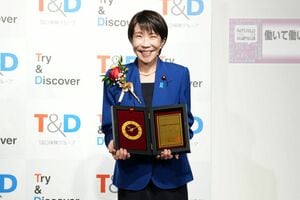役職定年によるモチベーションの低下が問題になってきた(写真:siro46/Shutterstock.com)
役職定年によるモチベーションの低下が問題になってきた(写真:siro46/Shutterstock.com)
一定以上の年齢に達すると、「部長」「グループ長」といった役職から外れる「役職定年」。多くの職場に浸透していたこの制度が近年、相次いで姿を消しています。なぜ、役職定年が廃止されているのでしょうか。そもそも、役職定年とはどんな狙いで導入されたのでしょうか。過去の経緯も交え、やさしく解説します。
「役職定年」が導入された事情とは
「役職定年」とは、役職ごとに定年を定め、それぞれの年齢に達したら自動的にその役職を退く制度です。
例えば、「課長」の役職定年が50歳に設定されている企業では、50歳になった際、課長より上位の役職に昇進できなければ、課長職を解かれてしまいます。解雇されることはありませんが、多くの場合、ラインを外れ、別の職位・ポストで働くことになります。
日本の企業に役職定年が広がったのは1990年代前半のことで、高齢化社会の到来と密接な関係があります。
まず、1985年に高年齢者雇用安定法が抜本改正され、定年を60歳とすることが努力義務になりました。その後、さらなる同法の改正が1994年に行われ(施行は1998年)、60歳未満の定年は法律の禁止事項になります。1980年までは多くの企業が定年を55歳としていましたが、定年延長によって来たるべき高齢化社会に備えようとしたわけです。
もっとも定年延長には大きな問題がありました。当時の日本社会は終身雇用制で、年齢に応じて基本給が上昇していく賃金体系も当たり前の時代です。そのため、定年を延長すれば、人件費の増大は避けられません。同時に、年齢の高い社員が増えすぎてポストが不足したり、若い世代の採用・登用の機会が減少したりしてしまう恐れも出てきました。
人件費の抑制と組織の新陳代謝。この2つを同時に解決する策として登場したのが役職定年制だったのです。