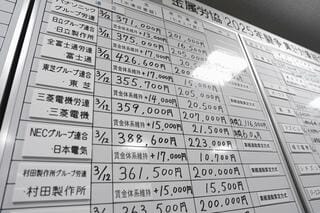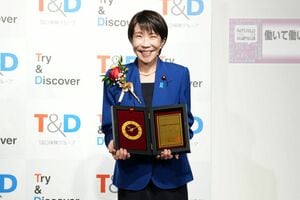年収が半減するケースも
今から30年前の1995年に産労総合研究所が実施した調査(上場企業を中心に221社が回答)によると、当時、役職定年を導入していた企業は52%で、2年前より8ポイント上昇していました。
同じ調査では、早期退職優遇制度を導入・検討している企業は6割超に達し、特に従業員1000人以上の大企業ではその割合が8割近くに上っていました。60歳定年の義務化に伴う組織の高齢化・硬直化を防止するため、企業が対策を急いでいたことがわかります。
役職定年制はその後、日本の多くの職場に広がり、定着しました。2000年以降に社会へ出た人にとって、自分の職場に役職定年があることは半ば常識だったことでしょう。役職ごとの定年を頭に入れ、将来のライフプランを思い描いたり、社内でのキャリア形成に励んだりした人も多いに違いありません。
では、役職定年制度はどのように運用されてきたのでしょうか。
人事院が定期的に実施している「民間企業の勤務条件制度等調査」を見てみましょう。役職定年制がほぼ行き渡ったと見られる2007年当時、役職定年の年齢は55〜57歳に集中していました。
そうした中、役職定年によって当人を格下のポジションとする企業の割合は部長級で37.5%、課長級で43.2%に上っています。
人件費の抑制も顕著で、課長級の役職定年後に「基本給」「賞与」を減額する企業の割合はいずれも約3割。「管理職手当」の廃止も4割近くになっていました。そうした結果、役職定年後の年収水準が「下がる」企業の割合は8割を超えていたのです。中には年収が半分になる企業もありました。
職場の新陳代謝という効果はあったものの、「出世できなければ、50代半ばで役職定年を迎え、年収も下がる」という流れが一般的になってきたのです。勤続年数が長くなるにつれ、役職定年による降格や収入減少という現実がわが身に迫り、働く意欲が減退していく人も多かったことでしょう。