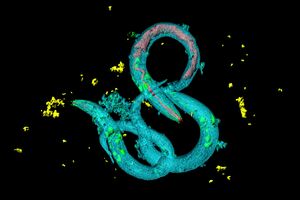DeepSeekの技術力には早速疑問の声も上がっている(写真:ロイター/アフロ)
DeepSeekの技術力には早速疑問の声も上がっている(写真:ロイター/アフロ)
中国企業が開発した生成AI「ディープシーク(DeepSeek)」。「スプートニク・ショック」になぞらえる声が上がるなどAI業界に衝撃を与えているが、その技術力を疑問視する声も上がっている。そんな疑問の一つが「蒸留」だ。蒸留という手法自体簡単ではないが、果たしてディープシークはどんな技術革新を生み出したのだろうか。(小林 啓倫:経営コンサルタント)
「スプートニク・ショック」に匹敵した「ディープシーク・ショック」
1月27日月曜日、週末明けの米株式市場を襲った「ディープシーク・ショック」。GPU(画像処理半導体)市場で圧倒的なシェアを誇るエヌビディアを筆頭に、AI関連株やIT関連株が広く売られ、株価が大きく下落した出来事を指す。
昨日の記事でも解説したように、これは中国のディープシーク社が発表した生成AIサービス(社名と同じ「ディープシーク」)、ならびにそれを支えるAIモデル(同社の最新モデルである「R1」)が引き起こした事件だ。
著名ベンチャーキャピタリストのマーク・アンドリーセンは、1957年10月4日のスプートニク・ショックになぞらえて、「ディープシークのR1は、AIにとってスプートニクの瞬間だ」という言葉で表現している。
スプートニク・ショックとは、旧ソ連が世界初の人工衛星打ち上げに成功したことで、当時の米国に流れていた宇宙開発・ミサイル開発技術の優位性という幻想が打ち砕かれた事件だ。つまりアンドリーセンの言葉は、それに匹敵する出来事がAIの世界で起きたということなのだが、いったいどういうことか。
この点について、改めて簡単に説明しておこう。
ご存知の通り、いまさまざまな生成AIサービスが登場して世間を賑わせているが、優秀なAIモデルは一握りの欧米企業によって独占されている。それは最先端のAIモデルを開発するには、エヌビディアが提供しているような最先端のGPUを大量に用意し、多額のコストと時間をかけてAIのトレーニングを行う必要があったためだ。
それこそ、まるでロケット開発でも行うかのように、高度な技術と膨大な予算が必要だと考えられていたのである。
ところが、ディープシークは、この前提を覆してしまった。なぜかというと、米国は少し前から、中国の台頭を警戒してAI開発に必要な半導体や関連技術の輸出制限を行っている。そのため中国のAI開発者は事実上、欧米のトップAI企業が開発に使用しているような、高度なGPUや開発環境を十分に利用できない。
そんな環境下にあるはずのディープシークが発表した生成AIサービス、そしてそこに使われているAIモデルは、OpenAIのChatGPTが使用している最上級モデルに匹敵する性能をたたき出したのである。
しかも、ディープシーク社は創業2年足らずで、従業員数も200名弱と見られている。さらに、同社の最新モデル「R1」を開発するのにかかったコストは、たったの560万ドルだと言われている。日本円にすると約8億円で、決して小さい額ではないのだが、それでも従来の予算と比べると10分の1程度のコストとなっている。
要するに、最上級のAIを作るのには高度な設備と多額の予算が必要だと思われており、だからこそ中国への技術輸出規制を行えばAI分野での米国の優位性が保たれると思っていたのに、その幻想をディープシークがあっさりと打ち砕いてしまったわけである。
 DeepSeekを創業した梁文峰(Liang Wenfeng)CEO(写真:©Unk/ROPI via ZUMA Press/共同通信イメージズ)
DeepSeekを創業した梁文峰(Liang Wenfeng)CEO(写真:©Unk/ROPI via ZUMA Press/共同通信イメージズ)