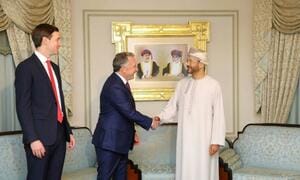総統に就任早々米下院議員団の表敬訪問を受け、マイケル・マコール下院外交委員長(左)から贈られたカウボーイハットを被る頼清徳総統(5月27日、提供:台湾総統府/AP/アフロ)
総統に就任早々米下院議員団の表敬訪問を受け、マイケル・マコール下院外交委員長(左)から贈られたカウボーイハットを被る頼清徳総統(5月27日、提供:台湾総統府/AP/アフロ)
「台湾統一は歴史的な必然だ」は詭弁
台湾の頼清徳新総統が5月20日の就任演説で行った中台関係に関する発言が波紋を呼んでいる。
頼清徳氏は、蔡英文前総統と同様に「現状を維持する」と述べる一方で、中国が掲げる「一つの中国」原則の完全否定とも受け取れる表現を多用した。
中国が強く反発している。
頼清徳氏は就任演説で「中華民国と中華人民共和国は互いに隷属しない」と訴え、台湾と中国の正式名称を用いて双方が対等の関係だと主張した。
蔡英文氏は2016年の就任演説で、中台を「(台湾海峡の)両岸」と呼び、明確に2国間の関係と位置付けることを避けていた(時事通信2024年05月22日)。
中国情勢に精通したジャーナリストの福島香織氏は、JBpresss紙上に「台湾・頼清徳の総統就任演説がすごかった! 中国を激怒させた『新二国論』、日本や米国に台湾の民主主義を守る覚悟は」と題する記事を投稿している。福島氏の主張は後述する。
ところで、中華人民共和国(以下、中国)と中華民国(以下、中華民国または台湾)は、1949年以降、それぞれが正統政府であると主張し、相手の存在を否定してきた。
中国は、台湾は中国の不可分の領土であり中華民国・国民党政府は不法に支配しているとして、台湾を開放し断固中国の統一を実現するという「台湾解放」を一貫して唱えた。
台湾側も「大陸反攻」「祖国統一」を主張し、大陸側とは妥協、接触、交渉しないという「三不政策」(1979~1991)を続けた。
この間1954年と1958年に台湾海峡の沿岸島嶼において2度にわたり軍事衝突が発生した。
国際社会にあっては1948年以降、中華民国政府(台湾)が国連の代表権を有していたが、1971年に中国側が代表権を獲得してからは立場が逆転した。
また、これと相前後して米中接近、日中国交回復が進められ、台湾の政治面での国際的孤立は次第に深まった。
これ以降、台湾は民間関係を主とする経済、文化、技術協力などによる実質外交時代を進めていった。
中台双方の台湾問題への対応は建国の指導者の逝去等に伴う世代交代によって変化がみられるようになった。
そして、中台の歴代の指導者は、台湾問題についてそれぞれ自らの考え方を発表してきた。
中国では、鄧小平の「台湾同胞に告げる書(一国二制度)」と「葉九点」、江沢民の「江八点」、胡錦濤氏の「胡六点」および習近平氏の「習五点」などがそれである。
一方、台湾では、李登輝の「二国論」、蔡英文氏の「華独」、そして頼清徳氏の「新二国論」などがそれである。
初めに、頼清徳総統の就任演説の概要について述べる。次に、中国の対台湾政策の変遷について述べる。最後に、台湾の対中国政策の変遷について述べる。
台湾問題の主要プレーヤーである米国の対中国・対台湾政策の変遷については拙稿「一触即発の台湾海峡、危機勃発の全シナリオ」(2020年12月17日)」を参照されたい。