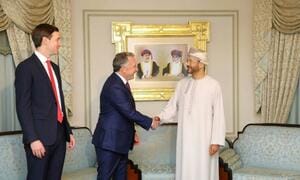ゼレンスキー大統領をホワイトハウスの入り口で出迎え固い握手を交わしたトランプ大統領だったが・・・(2月28日、ウクライナ大統領府のサイトより)
ゼレンスキー大統領をホワイトハウスの入り口で出迎え固い握手を交わしたトランプ大統領だったが・・・(2月28日、ウクライナ大統領府のサイトより)
ロシア宥和的姿勢によって高まる米国不信
米国のドナルド・トランプ大統領とウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領の口論を切っかけに両国関係に亀裂が生じ、いきなり米国はウクライナに対する軍事援助(情報提供を含む)を停止した。
それを不可欠としているウクライナに対し深刻な戦略的ダメージを与えたことは言うに及ばないが、同時にNATO(北大西洋条約機構)をはじめ、世界の米同盟国および友好国にも大きな衝撃を与えた。
トランプ大統領のロシアへの接近・宥和的姿勢とウクライナおよび欧州に対する冷淡な態度が同盟国の不安をいやが上にも高め、今後、NATOの安全保障・防衛に米国が関与しないのではないかとの見方が急浮上している。
早速、欧州には、米国の関与なしで欧州をどのように守るのか、米国不在の集団防衛体制はどのようなものになるのかなど、米国の参画・支援なしでロシアにいかに対処するかが、喫緊の課題として突き付けられ、再考を迫られている。
その課題は、これまで米国に大きく依存してきた米国の核の傘、すなわち拡大抑止に対しても向けられている。
フランスのエマニュエル・マクロン大統領は3月5日、ロシアは欧州全体にとって脅威であるとし、フランスの核の傘を欧州の同盟諸国に拡大することについて議論する用意があると述べた。
欧州の核保有国はフランスと英国のみであるが、米国の拡大抑止に対する不信から、欧州の核による抑止力を通じて欧州大陸の同盟国を守るための戦略的議論を始めようとの提案である。
ドイツでは、米国が長年抑えてきた核武装論が浮上している。
ドイツの新首相に就任することが有力視されている保守派のフリードリヒ・メルツ氏は、「フランスと英国の核抑止力を欧州全体に広げる議論を自国が始めるべきだと考えている」(下線は筆者)と、独紙フランクフルター・アルゲマイネ(3月9日付)とのインタビューで語った。
一方、ロイター(3月16日付)が伝えるところによると、米政府は、韓国を国家安全保障や核不拡散などの観点で注意が必要な「敏感国」に指定したという。
韓国では、朝鮮半島有事の際に米国が同盟国として守ってくれるのかとの疑念がくすぶっている。
北朝鮮の脅威を受けて韓国で核武装論が出ていることを踏まえた「敏感国」指定の措置とみられる。
なお、「敏感国」には、韓国のほか、中国、台湾、イスラエル、ロシア、イラン、北朝鮮が指定されているが、その中に台湾が含まれている点にも注目すべきであろう。
トランプ氏が大統領選挙に当選した後の2024年11月、台湾で行われた民間団体「台湾民意基金会」の世論調査で、中国の武力侵攻時に米国が軍を派遣して台湾に協力することを「信じない」と答えた人は57%と2020年9月の調査開始以来最多だった。
トランプ政権の誕生で、これまで見え隠れしてきた「疑米論」が台湾でも再登場しているのである。
国際情勢が予測不可能な方向に展開し、米国の拡大抑止の信頼性に対する疑念が高まる中、中国やロシアのような核軍事大国の脅威に曝されている国は、自前の核武装によって戦略的・戦力的劣勢を補わざるを得ないとの選択肢に傾斜する動きを強めているのだ。