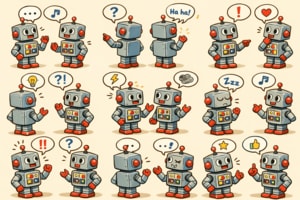連載:少子化ニッポンに必要な本物の「性」の知識
 雅(みやび)に見える平安時代の貴族社会と、いまの時代の世の中は似ているというのだが、その真意とは
雅(みやび)に見える平安時代の貴族社会と、いまの時代の世の中は似ているというのだが、その真意とは
美しく美徳的な姫君が、醜く悪徳的な老人の手によって、精神と肉体が崩漬させられる、倒錯的で嗜虐的な奇譚、『落窪物語』全4巻は、清少納言の『枕草子』、紫式部の『源氏物語』に先立つ10世紀末に成立する。
作者は不明だが、下級貴族の源順(みなもとのしたごう)など、男性によって描かれたものと考えられている。
『枕草子』にも『成信の中将は』の段に、「交野の少将もどきたる落窪の少将などは、をかし」とあるが、『落窪物語』巻4は、清少納言が『枕草子』成立以前に書き加えたとする説がある。
『源氏物語』や『枕草子』などの格調高い雅な王朝文学とは異なり、『落窪物語』には、当時、行なわれていた、「モラハラ」「パワハラ」「セクハラ」の様子が活写され、上流貴族の姫君に仕える、中下級の女房の視点から捉えられているとされる。
『落窪物語』の「落窪」とは、継母・北の方が主人公の姫君を、寝殿の隅にある一段低い落窪に住まわせて「落窪の君」と貶めたところによる。
主人公の姫君は中納言・源忠頼と、皇族の血筋を引いた母との娘との間に生まれた。
幼い頃に母親と死別した後、実父・中納言の元で、4人の娘を持つ継母・北の方とともに暮らしている。
継母・北の方や異母姉妹たちよりも、姫君(落窪の君)の出自の方が、はるかに高かったことを妬んだ北の方は、姫君を娘として扱わず目の敵にし、寝殿の床の一段低い落ち窪んだ部屋に閉じ込めた。
そしてお針子として大量の縫い物をさせたり、宮家の姫の実母から受け継いだ上等な調度品をほとんど取り上げて、自分の産んだ娘たちに使わせたり、食事も1日1食だけしか与えたりせず、衣服も真冬も薄着をさせて、侍女よりも見窄らしいものを着せたりするなど手酷く虐げていた。
父・中納言は、「他の娘たちの古着でも与えたらどうかね」と北の方に言うのだが、中納言邸の実質的な支配者だった北の方が、亭主の言うことを聞き入れることはなく、我が物顔でいられたのは、当時の母系社会における母親が強い発言権を握っていたことによる。
粗末な部屋に閉じ込められて、やり切れず、思い倦む生活を強いられた姫君。しかし、「生きたければ、かかるめも見るなりけり」と、遣瀬せない思いで静かに暮らしていた。
そんな姫の境遇に憐情していた侍女・阿漕(あこぎ)は、もともとは落窪の姫君の母親に仕えていた女房、没後は姫とともに北の方の屋敷にやって来た。
阿漕(あこぎ)の夫・帯刀(たちはき:太刀を帯びた役人)は、中納言邸に出入りしていた際に、利発だが慎み深く愛らしい阿漕を見初め通い婚の夫婦関係となる。
都で評判の貴公子・右近の少将・藤原道頼には多くの女友達がおり、縁談も多く持ち込まれるほどの色男。
阿漕(あこぎ)の夫・帯刀から、落窪の姫君の話を耳にした藤原道頼は、「おやつがわりに摘まんでやろう」と、最初は遊びのつもりで会いに行ったのだが、彼女を見た途端、その情感の匂い立つ艶容な姿に心に疼くものが込み上げた。
端正な顔容、澄み切った黒い瞳、柔らかな鼻の線、きめが細かい白い肌、どの部分を見ても貴婦人らしい優雅な線と官能美を匂わせる姫君。
外面的なその魅力もさることながら、言葉遣いに気品があり、奥ゆかしくも控え目、宮家仕込みの雅な礼儀作法、高い感性による和歌の秀逸さ、亡き母直伝の麗しげなる琴の才腕など、学問や芸術に抜きん出た、高い教養を併せ持っていた。
道頼が女性に対して夢幻的に描いていたのは、このような雅やかな美貌と、知性と情緒のある人となりだった。
姫君に見惚れた道頼は、ひたむきに彼女のもとに通い詰め、念願の契りを果たす。
落窪の姫君のもとに評判の貴公子・道頼が通っていることに嫉妬した継母・北の方は、「忌々しい落窪」と、彼女を庭にある粗末な塗籠(ぬりごめ:納戸)に、鍵をかけて取り篭めてしまった。