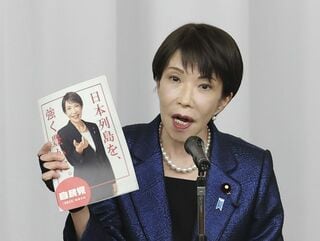日本の伝統「校倉造り」も「柾目」中芯材が貫き合う構造(唐招提寺経堂、著者撮影、以下同じ)
日本の伝統「校倉造り」も「柾目」中芯材が貫き合う構造(唐招提寺経堂、著者撮影、以下同じ)
奈良国立大学機構で会議があり、予定調整で少し時間ができたので、1300~1400年前の木材を見てきました。
法隆寺、唐招提寺など、日本の誇る「本物の木造建築」群です。
どこかで「木造は大規模建築に使われるようになったばかりで、まだ実験段階」という専門家の意見も目にしましたので、長年の補修を経ながら飛鳥、天平、また平安、鎌倉、室町期の木造建築が立ち並ぶ法隆寺で現場を確認しておこうと思ったのです。
冒頭の写真は唐招提寺(759年創建)に建っている、校倉造りの国宝「経蔵」です。
よく知られた「校倉」が、柾目の心材で構成されているのがよく分かると思います。
1400年前の大工さんは、21世紀のデザイン建築家より、よほど木材の叡智に通じていたことが 一目瞭然です。
「あぜくら造り」は「柾目材の劇場」
本当は、奈良国立大学機構の榊裕之先生(半導体)との打ち合わせの後、作曲家として長年の課題である「高丘親王航海記」(澁澤龍彦)のために、唐招提寺を見ておこうと思ったのです。
それはそれで、当初の目的は達したのですが、唐招提寺で目についたのが「木造建築」本来の材の使い方でした。
冒頭に引用した写真「経蔵」の隣にある、やはり高床式、校倉造「宝蔵」の礎石と柱を確認してみましょう。
 「あぜくら造り」の基礎、唐招提寺「宝蔵」
「あぜくら造り」の基礎、唐招提寺「宝蔵」
巨木から切り出した「中心材」というか、堂々たる丸太が16本、座りがいいように細かく調整された礎石の上に載っています。
言うまでもなく「柾目」の材が鉛直方向に構造を支えている。
そしてこれと直行する床面の柱が、またしても筋の良い柾目の心材が、きれいに直行する方向を貫いているのを確認しました。
 柾目材と柾目材が直交する「千年建築」
柾目材と柾目材が直交する「千年建築」
これでこそ「千年建築」たりうるわけで、伊達や酔狂で「校倉」は建てられていない。
ここにはこれ以上引用しませんが、「あぜくら造り」は、まさに「巨木心材・柾目材の劇場」というべき「筋の良い建築物」であることが、はっきり確認できました。
ここまできたら「正倉院」も他日確認してこないわけにはいきませんから、また次回予定されている京阪奈出張で、調整時間が取れたら、確認してこようと思います。
759年創建、1266年程度もっている唐招提寺にして、こうなのです。
足をほんの少し伸ばせば、607年創建、日本というより世界最古の木造建築として知られる法隆寺がありますので、車を回して確認することにしました。