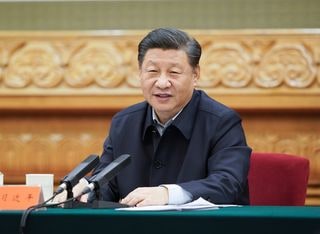以上、一帯一路が途上国でどのような問題を起こしているかを、典型的な事例に即してみてきたが、中国側は、一貫して、一帯一路は中国と途上国の双方にウィンウィンをもたらすとして、その意義を強調してきたが、実際上は、それは、(i)中国の国営企業にとっては請負事業増大の機会を*3、(ii)資機材のサプライヤーにとってはその資機材の輸出増の機会を 、(iii)国有銀行にとっては貸出増の機会を付与し、中国側には二重、三重の利益をもたらすものとなる一方、途上国にとっては益するところが少ない。そこでの「ウィン」は全て中国に帰属すると言って過言ではない。
他方、途上国にとっては、「自力では作れないインフラを中国の支援のお陰で手に入れることができるのだから、それは途上国にとってもウィンではないか」とする反論がありうるが、もしも、当該インフラの規模が適切で、途上国が自力で維持管理できるものであればそうとも言えよう。だが、その施設が過大で、必要以上に立派なものであれば、当該施設は、完成後、収益どころか、累積赤字を生むだけのものとなり、それは途上国にとってはルーズ(lose、負け)でしかない。加えて、後々巨額の返済義務が残るのであれば、それはウィンウィンどころの話ではなく、途上国にとってはまさにルーズ・ルーズとなる。
そしてたいがいの場合は、そのようになっている。
*3 当初から予想されている資機材の購入金額は、すでに請負契約の金額に含まれているため、この分は差し引いて考える必要があるが、施工期間中に発生するコストオーバーランに係る部分は貿易額の純増となる。
ついに軌道修正が
一帯一路は、2013年に導入されて以来、急速に広まっていったが、実はその投資額は2016年をピークに、2017年から減少に転じている。これは一つには一帯一路の当初の目的であった「国内の余剰生産力のはけ口」としての役割が一巡したことにもよるが、それだけではなく、上記でのべたような問題点が徐々に噴出し始め、受入国側で一帯一路に対する警戒感が高まってきたことにもよる。
このような問題事案の存在は、現地の状況に日々接する大使館・外務部においては既に認識されていたところであるが、これら外務部の認識・懸念は、政府部内で圧倒的な力を有する(一帯一路の主務官庁である)商務部の前にはかき消され、政府全体の意見とはならなかった。
しかし、このような現地での問題は、党中枢の耳にも入り始め、一帯一路の進め方について見直しが行われ、党幹部が主宰する一帯一路建設工作指導小組からの指示もあり、2018年4月に、これまで商務部中心に進められてきた一帯一路の推進体制は大幅に改革され、国務院に新しく「国家国際発展協力署」が設置されることになった。同協力署には、それまで商務部内に置かれていた対外投資経済協力司が移管され、その運営は国家発展改革委員会が主導し、商務部、外務部がこれに参加する形となり、政府部内で外務部の声がより強く反映されるようになったのだった。