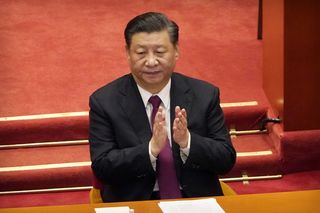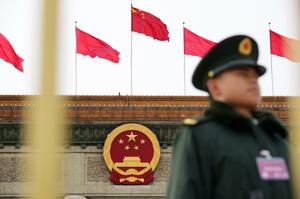外国勢の土地取得や企業買収についての危機感~幕末維新時との比較~
以上、主にデータやプラットフォーマー企業に関する国際的な状況を眺めつつ、日本の危機に関して書いて来ました。いまさら告白するまでもありませんが、私自身、インターネットの世界で起こっている現実について専門的に知悉しているわけではありません。また一般的な意味でも、先述のとおり、現在はいわば個人情報(≒石油)でいえば黎明期であり、「これから原油がポリエステルに変わって行く時代」と示唆したとおり、現時点では、まだ、このデータやプラットフォーマーを巡る動きの展開については、正確には先が見通しにくい状況です。したがって、真の意味で正しい危機感が持てるかについては、私も日本社会も正直、覚束ないところがあります。過度に恐れているのかも知れませんし、恐れ足りないのかも知れません。
ただ、リアリティを持って先が見通しにくいデータの帰趨以外の部分ならずとも、すなわち、よりタンジブルな明確なものに関しても、日本人は最近、全体的に原初的な警戒感や危機感に乏しいと思わざるを得ません。例えば、「日本の土地は中国勢に買われても、中国の土地は買うことが出来ない」という基本的なアンフェアな状況についても、「海外から投資してもらうことは良いことだ」という、ある意味でナイーブな極端な言説だけが重視されてきた感があります。
土地に関しては、特に、各地域での外国勢による基地周辺の土地の買い占めなどで危機感が高まり、ようやく先月、いわゆる「重要土地等調査法案」が閣議決定されました。注視区域についての土地所有の調査や、特別注視区域についての取引の事前届け出制が導入される見込みですが、正直、公明党からの反発などで、当初案からは緩まった印象もあります。
また、昨今、三洋電機の白物家電事業(ハイアール)や、東芝のテレビ事業(ハイセンス)などから、キラリと光る技術を有する中小企業に至るまで、中国勢による日本企業の買い漁りが話題になっていますが、逆はあまり聞きません。技術流出の危機感の高まりもあってようやく、昨年、改正された外為法や関連政省令・告示が施行されましたが、どれほどの歯止めになるでしょうか。
本来、最近は、むしろ例えばIT技術に先行する中国企業の買収を日本企業が考えても良い局面ですが、ほとんど耳にすることはありません。有名な深圳地区でのスタートアップ投資にしても、米国のベンチャーキャピタル(VC)が深圳の中国のスタートアップ企業に投資している例は枚挙にいとまがありませんが、日本のVCがそういう展開をしているという事例は寡聞にして殆ど聞いたことがありません。
この点に関しては、中国側が共産党政府の下でガッチリ守っているという体制の問題もさることながら、かつての日本人や日本政府から見たら嘆かわしく思うようなマインドセットの差が如実に出てしまっている感じがします(要は、日本人や日本企業の多くが待っているだけで攻めて行かない)。中国のみならず、対米国でも、インドや東南アジア諸国に対しても、受け身だからです。いずれにしても、「投資してもらうことは良いことだ」という、どこかの途上国が貧困を脱するために切望するようなレベル感だけで物事を判断するのは危険だと感じます。アンバランスな状況を前に、奮起しなければならない状況ではないでしょうか。
以上、ここまで、情報(個人データなど)の貴重な「資源」獲得競争に加え、その実質的支配をする企業や開発者の取りあい、はたまた、より直接的で見えやすい土地の取りあいや先端技術の取得合戦に関し、長々と述べてきましたが、結論的には、日本人も日本企業も日本政府も、少なくとも国際的な感覚からは危機感が薄いと思わざるを得ません。いかに危機を早く察知して、迅速に対応・行動するかは、国家や組織が基本的に取るべき姿勢です。昔は全て良かったというつもりはありませんが、かつての日本は明らかに今とは違っていました。
今から150~200年ほど前の日本人は、外国勢が日本近海に近寄ってきているという状況や(1792年や1804年のラクスマンやレザノフといったロシア船の来航)、長崎でちょっとした乱暴狼藉を働く(1808年の英国船のフェートン号事件など。オランダ商館員を人質に水や食料を要求)といった事態に、危機感を抱き、異国船打ち払い令を出したり、逆にアヘン戦争での清国敗北の報への恐怖から、薪水給与令を出したりした。極め付きは、必ずと言って良いほどに皆が学ぶペリー来航とそれを引き金とした最小限の開国ですが、幕閣は、悩みながらも、海外勢を正しく恐れ、攻め取られることを警戒しつつ、ある程度の抵抗もするなど、ギリギリの外交を繰り広げていたと言えます。
ちょうど昨日(4月4日)放映されたNHK大河ドラマ『青天を衝け』では、渋沢栄一やその仲間(当時、武州の農民)レベルの民衆ですら、尊王攘夷の思想に影響されて決起することが示唆されていましたが、海外勢による日本への進出・租借地などの取得を、国を挙げてかなり警戒していたことは間違いありません。
現代で言えば、例えば香港を横目にみて、「アヘン戦争で香港がイギリス領になったが、一寒村にすぎない同地が独立は保ちつつも貧しいままでいるのと、植民地にはなるものの経済的に物凄く繁栄して豊かになるのと、香港の人々にとってどちらが良いであろうか」という大議論が生じても不思議はないわけですが、「とにかく外国勢は入れない」という過激な攘夷思想が国を覆っていました。貿易面での健全な開国論は多少ありましたが、「排外」ということについては、国民的には、ほぼ議論の余地がなかったと考えてよいでしょう。
こうした「熱病」のような尊王攘夷の世論は、後世から見れば、大いにバランスを欠いていることは確かです。所詮、当時の欧米勢とまともに戦って勝つ可能性は低く、実際にその後の歴史の経緯を見れば、元々は「今の幕府では攘夷はできない」と真の尊王攘夷の実現を掲げて決起し維新を起こした勢力が、何とその後明治政府を成立させた後、自ら洋装をして開国してしまうという皮肉な結果に陥ることになります。かなり極端な間違った議論と、それに基づく命がけの実際の行動を多くの「志士」たちが展開していたことは間違いありません。
しかし、こうした過敏とも言える海外勢への対抗意識や警戒感が、維新後の富国強兵や殖産興業の原動力になっていたこともまた事実です。つまるところ、異なるものを受け入れるという受容性と異なるものを警戒するバランスが、社会としての健全な成長を促すというのが歴史の教訓だとも感じます。その点、現代は、あまりに警戒が薄れてしまっているのではないでしょうか。逆の意味でバランスが悪いと思わざるを得ないのです。