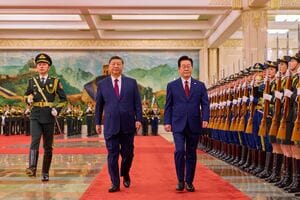「開かずの扉」再審制度の問題点とは
再審制度は刑事裁判で誤判を受け、無実なのに有罪の確定判決を受けた人(冤罪の被害者)を救済する制度のことです。誤判によって、無実の人を処罰することは許されません。懲役刑や禁錮刑でも大問題ですが、冤罪で死刑が執行されたら取り返しがつきません。
再審制度は刑事訴訟法の第4編「再審」、条文で言えば第435条〜第453条に記されています。「再審法」という名の法律はありませんが、刑訴法の当該条文を便宜的に再審法と呼び、その改正を求めることを「再審法改正」と称しています。
 袴田事件は再審開始まで請求から40年以上がかかった。写真は2023年3月、東京高等裁判所の再審開始決定に喜ぶ弁護団(写真:山口フィニート裕朗/アフロ)
袴田事件は再審開始まで請求から40年以上がかかった。写真は2023年3月、東京高等裁判所の再審開始決定に喜ぶ弁護団(写真:山口フィニート裕朗/アフロ)
再審に関する刑事訴訟法の規定によると、再審請求ができるのは、(1)原判決の証拠が偽造、変造、虚偽であったことが証明された場合、(2)無罪などを言い渡すべき明らかな新証拠が発見された場合、などに限られています。実際に再審請求が行われるのは、ほとんどが(2)のケースですが、そのハードルが極めて高いのです。
日本では、捜査機関によって収集された証拠は、すべて法廷に提出されるわけではありません。検察は被告人の有罪を立証するのが目的であり、集めた証拠の中から選んだものを提出します。
「被告人が犯人でない可能性を示す証拠」を法廷に提出する義務がないということは、検察に不利な証拠はいつまでも隠すことができることを意味します。つまり、弁護側は「膨大な時間と人員を使って集められた証拠のうち、検察が選んで提出した証拠」をもとに被告人の弁護をしなければなりません。
したがって、裁判官もすべての証拠を見て、被告人の有罪・無罪を判断しているのではなく、検察が選んだ証拠、および弁護側が集めた証拠(検察側に比べて圧倒的に少ないのが通例)のみで判断を迫られているわけです。しかも判決が確定した後も被告・弁護側にはすべての証拠を見る権利がありません。
再審請求には「無罪などを言い渡すべき明らかな新証拠が発見」されることなどが必要ですが、検察が隠している証拠がある以上、新証拠の発見は容易ではありません。このため、日弁連は法改正の第一の要点として「警察や検察が持っている証拠をすべて開示させる」こと、すなわち「全証拠の開示の制度化」を挙げています。