ホンダがEV戦略を大幅修正、市場低迷とトランプ政策で打撃…四輪事業の生き残りは日産との統合再交渉の行方次第か
2025.5.23(金)
ここからは、JBpress Premium 限定です。
カンタン登録!続けて記事をお読みください。詳細はこちら
あわせてお読みください

日産、2万人削減でも足りない?高額報酬の外国人出向者、トランプ関税…大リストラでも問題だらけ、再生見通せず
ゴーン時代の「リバイバルプラン」と違いすぎる周辺環境
井上 久男

日産をダメにした「スピード不足」、エスピノーサ次期社長はどう立て直す?問われる社外取締役の自浄能力
井上 久男

福岡県の人口最少市、豊前市が台湾に抱きつくワケ…TSMC効果、北部九州の人材争奪戦は少子高齢化対策のチャンス
井上 久男

日産内田社長が退任見通し、後任選びのカギ握る指名委員会に重大責任…テスラとの提携話はなぜ浮上したのか
ホンダと鴻海が連携して日産に出資する案も
井上 久男

【ホンダ・日産統合破談の内幕】日産、「自力再建」へちゃぶ台返し…再建計画に不満抱くホンダの子会社化案に反発
ホンダは内田社長に、日産はホンダの変わり身の早さにそれぞれ不信感
井上 久男
自動車の今と未来 バックナンバー
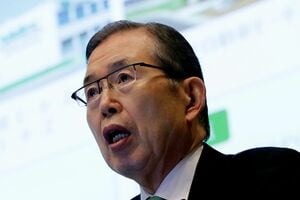
ニデックにアクティビストの影、ガバナンス不全で永守氏の院政も…“イエスマン”の社外取では「第2の創業」は遠い
井上 久男

【試乗レポート】スバル新型「フォレスター」で1400km!ストロングハイブリッド、ガシガシ系を卒業した6代目の実力
桃田 健史

【2026年の自動車業界】破談から1年、日産とホンダは再統合へ向かうのか──技術提携だけでは埋まらない課題
井元 康一郎

【2026年の自動車産業】中国に負ける日本、ハード・ソフトで圧倒的な差も…現実を直視し技術を「盗み返す」べき理由
井上 久男

日本で販売減のボルボ、だが改良版「XC60」1200km試乗で見えた“静かなプレミアム”路線の強み
井元 康一郎

川崎市が挑む「モビリティハブ」、静かに進む都会の「陸の孤島化」の救世主になるか?
桃田 健史



