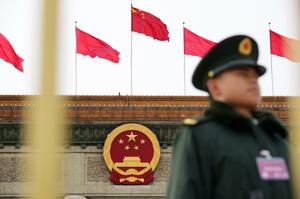学生側の動きが鈍かった「女性排除サークル問題」
矢口:それも間違いではありません。一方で、学生自身が考えた結果が一部の人間を差別し、排除するものであった場合、それを放置することも到底正しいとは思えません。
残り3465文字
矢口:それも間違いではありません。一方で、学生自身が考えた結果が一部の人間を差別し、排除するものであった場合、それを放置することも到底正しいとは思えません。
残り3465文字
ここからは、JBpress Premium 限定です。
カンタン登録!続けて記事をお読みください。詳細はこちら