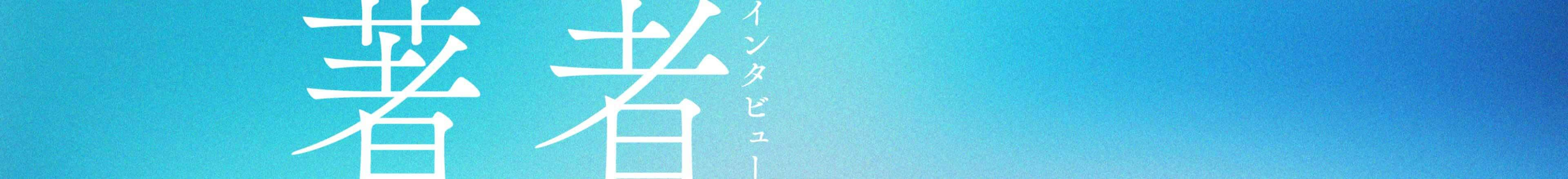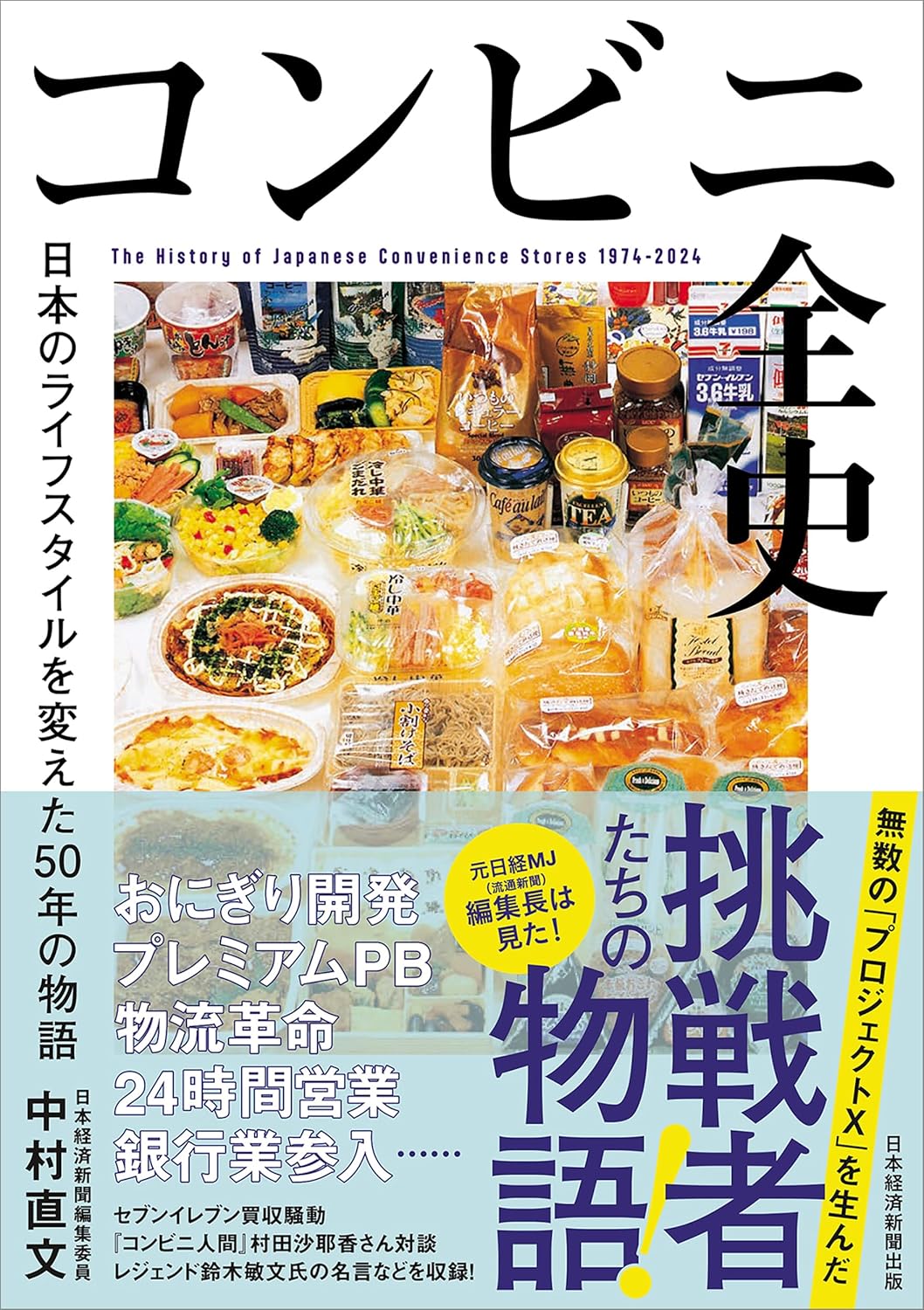出所:共同通信イメージズ
出所:共同通信イメージズ
いまや社会のインフラといっても過言ではない「コンビニエンスストア」。セブンイレブンが1号店を開店した1974年から半世紀が経過した現在、全国に店舗数は5万店以上、売上総額は11兆円を超え、年間約160億人が利用するといわれる。しかし、新規出店ペースはピークを越え、業界は曲がり角を迎えている。これからのコンビニはどうなるのか――。2024年12月に『コンビニ全史 日本のライフスタイルを変えた50年の物語』(日本経済新聞出版)を出版した日本経済新聞編集委員の中村直文氏に、現在のコンビニ業界の状況や、セブンイレブンの成長を支えてきた戦略について聞いた。
コンビニ業界は拡大一辺倒から「持続性重視」へ
──著書『コンビニ全史 日本のライフスタイルを変えた50年の物語』では、近年コンビニ各社が大きな戦略転換を図っている点に触れています。今、業界全体としてどのような状況にあるのでしょうか。
中村直文氏(以下敬称略) 2024年、コンビニ業界は過去最高の売上高を記録しました。しかし、業界全体としては曲がり角にあると考えています。その背景にはいくつかの要因があります。
1つ目は、人手不足の深刻化です。オーナー自らが長時間労働を余儀なくされる状況が増え、店舗運営の負担が大きくなっています。2つ目は、国内の人口減少と少子高齢化の進行です。人口が減少する中では消費が右肩上がりに成長することは考えづらいため、近年の出店ペースは鈍化しています。2010年代はコンビニ各社が毎年1000店ペースで出店していましたが、2018年をピークに総店舗数は停滞しています。
──なぜ、2010年代はそれほど好調だったのでしょうか。
中村 きっかけは東日本大震災です。コンビニは2000年代に「魔の10年」といわれる停滞期を迎え、その状況を何とか打開しようと各社プライベートブランド(PB)をつくったり、経営戦略の転換を進めたりしていました。
そうした状況下で、震災によって関東を中心に食料の入手が困難になる中、「コンビニは便利だ」という認識が消費者の間で広がったのです。それまで多くの女性や高齢者はコンビニでの買い物に抵抗を感じていたようですが、震災で不便さを経験したことで、コンビニの利便性に気づく人が増えたと考えられます。
働く女性の増加も大きな要因です。こうした追い風の中で各社が成長の可能性を見いだし、大型投資を本格化させたのが2010年代でした。しかし、2010年代後半から人手不足が深刻化したことで、コンビニの出店ペースは減速します。だからこそ、2020年にコロナ禍が到来した際、コンビニ業界は巻き返しを試みました。外出機会の減少によって、家の近くにあるコンビニの用途が見直されると考えたのです。