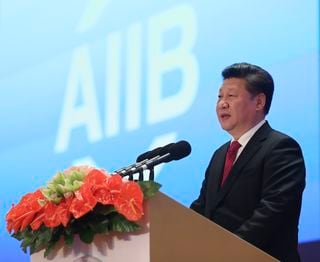特攻機としても使われた一式戦闘機「隼」
特攻機としても使われた一式戦闘機「隼」
(聞き手・構成:坂元 希美)
8月に入ると多くの地域でお盆を迎える。先祖の霊があの世から帰ってくるという時期に故郷へ帰り、家族・親族と墓参りをして故人に思いを馳せながら、生きている者同士で旧交を温める人も多いだろう。また、この頃に彼岸へ行った人たちのことも思い出されるかもしれない。太平洋戦争で戦死した人たちだ。彼らはこの季節、どこに帰ってくるのだろうか。
「戦死」の定義は軍人が戦争や戦闘で死亡することであり、命を賭けることが織り込まれた職業で想定されている死だ。その職業は今もこの国に存在している。自衛官だ。
現在、彼らは戦争や戦闘に参加してはいないし、させないようにしているのだから「戦死」は想定外とされている。しかし、考えられなかった、ありえないことだった・・・つまり、「無いはずのこと」にしたままでよいのだろうか。「繰り返してはならぬ」とした過去の戦死についても、私たちは自分ごととして向き合っているだろうか。
「戦死」について、思考停止ではなく、向き合い方を考えようと提案している社会学者がいる。帝京大学准教授の井上義和氏だ。
 井上義和・帝京大学准教授(撮影:URARA)
井上義和・帝京大学准教授(撮影:URARA)
井上氏は教育社会学者として「戦跡の歴史社会学」研究プロジェクトに参加するうちに、奇妙な「戦死への向き合い方」に気付いた。2000年前後にメディア露出を始めた特攻隊ものである。小説や映画といったエンターテインメント分野だけでなく、ビジネスや生き方の自己啓発に特攻隊が取り上げられるようになっていた。特攻隊員の遺影や遺書が展示されている鹿児島県の知覧特攻平和会館には、年間60万人前後が訪れる。井上氏は過去と未来の戦死者がこれまで九段(靖国神社)と市ヶ谷(殉職自衛官慰霊碑)に引き裂かれてきたのに対して両者の橋渡しをするヒントが知覧にあるのではないかと考え、「ちょうどいい、節度ある、穏健な」戦死観を模索するたたき台として今年2月に上梓したのが『未来の戦死に向き合うためのノート』(創元社)である。
いまの時代に戦死をどう捉え、向き合えばいいのだろうか。井上氏に聞いた。