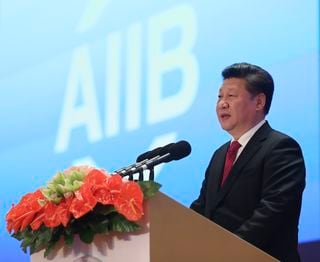――昭和の感覚で言えば、特攻隊員は家庭人としても社会人としても志半ばでバトンを国家に奪われた存在です。だから「それが二度とあってはならない悲劇だ」とか、「自分や周りの人がそうならないように」と考えてしまうのですが。
井上 「命のバトンリレー」は直系の血でつなぐ継承だけではなく、社会の中で先人の業績を評価したり、自分の仕事が後世の礎となったり、という形での継承もありますし、赤の他人でも誰かの役に立っているということも中継者になります。本書で取り上げた自己啓発本は、ほぼ全てがこのバリエーションです。「命のバトンリレー」のロジックは過去の戦争では都合よく使われてきましたが、平和な時代でもそのパワーが失われているわけではありません。
命のメッセージは突き刺さる
――「命のバトンリレー」の中継者だと実感できない、あるいは中継者でなくなることは、苦しく、生きづらさを感じることになるわけですか?
井上 特攻隊員のバトンは私たち自身や社会に託されています。70年以上前に書かれた特攻隊の遺書を読んで、「後を託す」「未来の日本は平和になってほしい」という言葉を自分宛てのメッセージとして受け止める人たちが出てくるのです。時を超えて「ビーン!」と突き刺さるわけです。私は託された、と。それは例えば、親から大事にされていないと感じている人や社会からもつまはじきで注目されず、誰も助けてくれないと思っている人、結婚しなかったり、子どもを持たなかったりして自分の人生は孤独だと思っている人や「生きづらさ」を感じている人たちにとっても、届きうる力を持っている。
それは、70年が経ったからこそ届くメッセージだとも言えます。70年という時間が、天皇や国家の名のもとに、無謀な戦争を戦ったとか、兵士の命を粗末に扱ったというネガティブな意味合いを削ぎ落し、シンプルに言葉とそのパワーだけを受け取ることができる状態にしているんです。そうして「孤独な自分もリレーの中継者だ」という意識を持てると、「やることがあるかもしれない。それならよく生きていこう、善きことをしよう」と思うわけですね。自己啓発書の感想やネットのレビューで「自分もちゃんとしなきゃ」という言葉がよく出てきますが、「ちゃんとする」のは特攻隊員の視線を感じられるから。自分の内側から出てくる意識ではないのです。
 井上氏は大量の「特攻」関連本と自己啓発系書籍を読み込んだという。写真はその一部(撮影:URARA)
井上氏は大量の「特攻」関連本と自己啓発系書籍を読み込んだという。写真はその一部(撮影:URARA)
――しかし、遺書自体は彼らの本心ではなく、バトンリレーから降ろされることを拒否できない苦悩や思いなどを省いて、残される人たちに苦痛を与えないための、あるいは見せたいポジティブな自分だけを表現するためのメッセージです。しかも、戦闘機搭乗員に選ばれるほどの優秀な人たちですから、表現方法もたくさん持っていました。出撃までに遺す言葉を磨きあげる時間があったから、パワーのある言葉になったとも考えられるのではないですか。
井上 私も特攻隊員の遺書を読みましたが、それが本心のすべてを書いたわけではないと知っていても、そこに綴られた、研ぎ澄まされた言葉はスーッと心に入ってきて、何かとつながる不思議な感覚をおぼえました。
彼らは究極的に、「死にたくないけれど死ななければならない」存在でした。それゆえの研ぎ澄まされた言葉が突き刺さる現代の孤独な人たちは、だからといって、突き刺さらなかった人を「日本人としておかしい」などと排除したりはしません。自分が大切な誰かや次世代のために働くだけなのです。実際、彼らに接しても排除は感じませんでした。ただ自分にできることは何かと利他的に考えています。