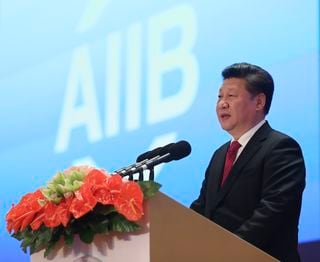戦死者への共感・同情ではない
――突き刺さった人たちは、特攻隊員の「死」を見ているわけではなく、彼らの残したポジティブ・イメージをリレーしているわけですか。特攻隊員への共感や同情ではないのでしょうか。
井上 共感や同情は、こちらが相手に寄せていくものですよね。それに対して、特攻隊員から受け取ったバトンは、勝手に向こうから届く、あるいは降ってくるんです。受け取る人は能動的に何かを取りにいったわけではなくて「受け取ってしまった!」と受動的に感じるわけで、ある意味、宗教的な覚醒に近いのかもしれません。相手の気持ちをあれこれ想像して、共感や同情することとは違うと思います。
私は特攻の自己啓発的な受け止め方に注目したのですが、世間的には、いわゆる平和教育的な受け止め方が主流です。平和教育は学校や、新聞・テレビなどのマスメディアがつくるガッチリした枠の中にあり、私たちはその内側で教育を受け、「正しい」ものの見方や考え方を身につけます。子どもたちとそれを啓蒙する知識人がいて、その両者をつなぐのが学校とマスメディアという関係です。
でも、枠の外側には広大な世界があります。マスメディアの外側にはインターネットやSNSがあり、そこでは内側の論理が通用するとは限りません。そして学校の外側には、枠の影響を受けない企業経営者やスポーツ選手、芸能人などがいて、彼らを媒介して力のある「強い言葉」が流通しています。特攻の歴史を語るときに、戦争の悲惨を訴え責任を厳しく追及するのは内側で通用する「正しい言葉」ですが、「強い言葉」は、特攻隊員の遺書や言動からポジティブな力を引き出します。自己啓発というのは「強い言葉」です。外側の世界に触れると「学校では教えない歴史の真実を知った」「新しい気づきを得た」となるのでしょう。
誰も戦死を語る言葉を持っていない
――過去の戦死が魅力的に映ると、戦争を肯定するような考えや、自己犠牲を美徳とするような「悪魔合体」が出てくるのではないかと恐ろしくなるのですが。
井上 「悪魔合体」への懸念や嫌悪感は、枠の内側から出てくる発想で、外側の人たちを排除しかねません。
かつても、学校とマスメディアの枠組みはありましたが、枠の内外(2つの言葉)をつなぐ「戦争体験世代」という存在がありました。とくに最も多く戦死者を出した1920年代前半生まれの人たちです。社会の中での彼らの存在感が大きかったときは、「正しい言葉」も「強い言葉」もためらいがあり、割り切れなさや遠慮のある抑制的なものでした。
しかし2000年代になって戦争体験世代の存在が薄くなり、「正しい言葉」と「強い言葉」が分離していきます。本書の表現を用いれば、知識と感情が乖離して、歴史認識の脱文脈化が起こります。特攻にまつわる「強い言葉」がストレートに心に刺さるようになる人が増えてくるのは、1920年代前半生まれの存在が薄くなってきたことと関係があると、私は考えています。
もはや枠の内側の「正しい言葉」で「強い言葉」を完全に抑え込むことはできません。外側の刺さった人たちは「強い言葉」が通じる者同士だけでつながりあっていこうとしますが、「強い言葉」を刺さるだけではない「つながる言葉」にして、戦死を考えてほしいですね。本書を読む枠の内外どちらの人にも「つながる言葉」を持ってほしいと願っています。
特攻隊員から受け取った言葉や、そこから呼び起こされる感情は鋭利なナイフのようなものです。70年の時を経て複雑な感情は背景の知識といった鞘がなくなり、ナイフが、抜き身のままで、言葉でつながっていない枠の両側の人の前に置かれているのです。自己啓発本の著者に私の本を読んでもらったら「自分たちがやっていることを初めて客観的に書いてもらって、不思議な感じでした」という感想をいただきました。信念をもってやっている実践でも、自分でじゅうぶんに言語化できるとは限りません。善きことに役立てていたはずのナイフでも、別の人の手に渡れば、意図せざる用途に使われる可能性もあるわけですから、ナイフを収める鞘として「つながる言葉」が必要なんです。
――枠の内にも外にも「つながる言葉」がないということは、この本のタイトルになっている未来の戦死、つまり自衛官の戦死を誰も語ったり、考えたりすることができないということになりますね。
井上 そうです。今もし戦争が起こっても、政府は戦死を語る言葉を持っていません。ただ死者が出るだけです。先述したナイフの悪用の最たるたるものは、特攻隊員の遺書を利用して人々を戦争に動員することでしょうが、さすがにそれは考えにくい。むしろ問題なのは、「未来の戦死」を想定外にしたまま語ろうとしない、宙づりの現状のほうです。だからこそ余計に、「過去の戦死」にまつわるナイフの美しさのみに関心が集まりやすい、とも言えます。
「専守防衛なら戦死者は出ないだろう」
――自衛隊の存在は災害出動も含め、私たちの暮らしに当たり前のものになっています。しかし、「戦闘に巻き込まれて死ぬような状況は認めたくない」というのが一般市民の感情としてあります。
井上 専守防衛の枠内であれば自衛隊の戦闘行為を「やむを得ないこと」として認める人は増えてきていますが、にもかかあらず、私たちの社会は「戦死」に向き合えていません。これは集団的自衛権や憲法改正以前の問題です。「専守防衛なら戦死者は出ないだろう」と、どこかで思っているのではないでしょうか。
しかし、現在でも訓練や任務中の事故で亡くなる自衛官はいます(警察予備隊以来の殉職者数は2018年追悼式の時点で1964柱)。彼らは、「死」がすぐそばにあることを承諾し、職に就いているのです。なのに、仕事で命を使った、まさに使命を果たしたのに偶然や不幸なこととされてしまう。日本という国家が存立するために、自衛官の命を使うことは織り込まれています。いわば、国家の「命のバトンリレー」を彼らが負っているのです。一般市民である私たちは、その事実を直視しようとすると苦しくなるでしょう。市民社会の論理では、軍隊や戦争、戦死というものはすっきりと位置付けられないし、正当化できないんです。
亡くなった自衛官の慰霊行事は、毎年10月に市ヶ谷の防衛省敷地内で政府関係者と遺族だけが参加する閉じられた中で行われています。一方で九段にある靖国神社では、誰もがそこを訪れてお参りし、思いを馳せることができます。これは「自衛官を靖国神社に入れろ」という話ではありません。政府が自衛官の死を見えないように、国民は見ないようにしているということを知ってほしいのです。私は本書を執筆する前に、殉職自衛官慰霊碑に参拝しました。遺族でも自衛隊関係者でもない、一国民として参拝したいと連絡をしたところ、関係者でもメディアの取材でもない一般人が参拝に訪れることは記憶にないと言われました。
――軍隊や戦争、戦死を市民社会の中に位置づけるのは、日本ではファンタジーしかないでしょうね。過去の戦死はバトンとして降ってきて、未来の戦死はブラックボックスに入れられている状態は、これからどうなっていくのでしょう。
井上 命のメッセージがダイレクトに降ってくることと、いざとなったら不死身の守り人が助けてくれると想定することは、コインの表裏の関係にあると思います。軍隊や戦争や戦死を位置付けないまま、命の問題に向き合うことを避けてきた結果でもあります。「節度ある戦死観」を確立しないと、この国は「日本では戦闘で人が死ぬなどありえない」という非現実的な想定から抜け出せない。それでは何らかの事態で「戦死」が現実になった時、社会がヒステリー状態になってしまうでしょう。命の問題に向き合うためには、枠の内と外で分断された「正しい言葉」と「強い言葉」の溝を埋める「つながる言葉」を、私たち自身の言葉として鍛えていく必要があると思っています。私は、両者はきっとつながると思っています。