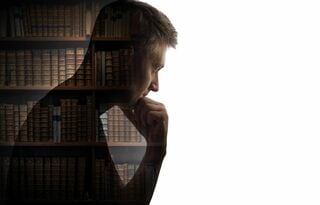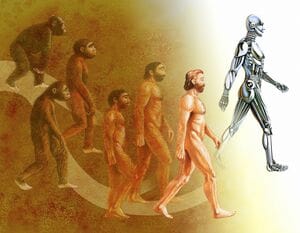時間は絶対的な実体なのか(写真:Sunlight_s/Shutterstock.com)
時間は絶対的な実体なのか(写真:Sunlight_s/Shutterstock.com)
【前編から読む】
◎時間の進み方は「直線」か「円環」か、トランプ2.0を生きる私たちの未来と行動を宗教観から考える
(堀内 勉:多摩大学大学院教授 多摩大学サステナビリティ経営研究所所長)
時間は「絶対的な実体」と想定したニュートン
時間とは何かという問いは、単なる測定の単位ではなく、自然の成り立ちや宇宙の構造を理解するための根源的な問いとして、古典物理学から現代物理学に至るまで、繰り返されてきました。ここでの最も基本的な時間の理解は、「出来事の前後関係を表す尺度」です。
例えば、石が落ちる、リンゴが熟す、星が爆発する・・・こうした出来事が「いつ起きたか」「どのくらいの速さで起きたか」を記述するために時間が使われます。その意味では、時間というのは変化や運動を記述するための枠組みであり、物理学における力学や熱力学、宇宙論など、あらゆる分野に関わっています。
古典物理学、特にニュートンの世界観では、時間は「絶対的な実体」として想定されていました。ニュートンは、空間と時間はそれ自体で存在しており、世界の出来事はその中で起こると考えました。ここでは、時間は常に一定の速度で流れ、誰にとっても同じように進みます。いわば、時間は神が世界を秩序立てるために用意した舞台装置のようなものです。
この考え方は、私たちの日常的な感覚にも合っています。私たちは普通、時計の針が同じ速度で動き、時間はすべての人にとって共通していると考えています。
しかし、20世紀以降の物理学は、それまでの素朴な時間観を根本から揺るがしました。アインシュタインは、特殊相対性理論によって、「時間の進み方は観測者の運動状態によって異なる」ことを示しました。光速に近い速度で運動する物体に乗っている観測者にとっては、静止している観測者に比べて時間が遅く進むのです。
これは「時間の遅れ(タイム・ディレーション)」と呼ばれ、時間が絶対的かつ一様に流れるというニュートン的な時間観を否定するものでした。
更に、アインシュタインは、一般相対性理論によって、時間が重力の影響によっても変化することを示しました。強い重力場の中では、時間はよりゆっくり進みます。例えば、地球の表面にいる人よりも、地上より高い場所にいる人のほうが、わずかに時間が速く進みます。
この「重力による時間の遅れ(グラビティック・タイムディレーション)」は、理論上の効果にとどまらず、GPS衛星のような高精度なシステムの設計において現実的に考慮されています。
こうして、時間はもはや誰にとっても均一に流れる背景ではなく、空間と結びついた、観測条件によって変化する相対的な構造、即ち、時空の一部として理解されるようになったのです。