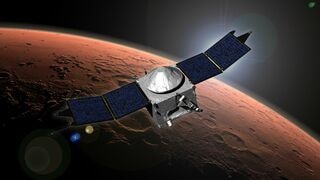超新星2022jliの想像図。生命のすむ星の近くで超新星爆発が起こったら、いったいどうなるのだろうか。 Image by ESO/L. Calçada
超新星2022jliの想像図。生命のすむ星の近くで超新星爆発が起こったら、いったいどうなるのだろうか。 Image by ESO/L. Calçada
(小谷太郎:大学教員・サイエンスライター)
超新星は宇宙最大の爆発現象です。昨晩まで何もなかった(ように見えた)星空の一角に、忽然(こつぜん)と新しい星が出現し、その輝きは凡百(ぼんぴゃく)の恒星や銀河を圧倒します。天文研究者は超新星爆発が大好きで、常にどこかの望遠鏡が超新星を探して夜空を見張り、新しいのが弾ければとたんにあらゆる種類の観測装置が突き付けられて貪欲にデータをむさぼります。
何万光年も何億光年もの彼方で弾けた超新星は見て楽しい宇宙花火ですが、その隣の星では強烈な電磁波や衝撃波や重力波や放射性核種が降り注ぐ大騒ぎとなっているでしょう。もしも爆発の近隣に生命の住む惑星があらば、その表面はきれいに消毒されてしまいます。
最新の見積もりによれば、地球の表面を多細胞生物がにょろにょろと這い回るようになったここ5億年ほどのあいだに、約2発はそうした超新星が近隣で弾けてもおかしくありません。過去5回起きた大絶滅のうち、オルドビス紀末とデボン紀後期に起きた大絶滅は、ほどよい距離の超新星が犯人だった可能性があります。
1億年に1度は大絶滅でクリーンな地球に
大絶滅とは、地球上の生物種の多くが一斉に絶滅する事件です。化石を調べると、ある地層と次の時代の地層で生物の様相ががらっと変わることで、大絶滅が起きたことが分かります。
そういう化石の断絶はいくつもあるのですが、特に著しい断絶が地球史に5回刻まれていて、「ビッグファイブ」などとあだ名されます。古いものから列挙すると、4億4400万年前のオルドビス紀末、3億7200万年前のデボン紀後期、2億5200万年前のペルム紀末、2億100万年前の三畳紀末、6600万年前の白亜期末です。
こうしてみると大絶滅はなんだか地質学年代の「末」や「後期」に集中して起きているように見えます。「○○紀中期の大絶滅」はめったにありません。これは当然で、地質学年代というものは、地層から出てくる化石などによって人間が区別して呼び名を付けているからです。大絶滅が起きた時期より前にできた地層と後にできた地層で化石の種類が変わるので、それらの地層に違う年代名がつきました。大絶滅は地質学年代をチェンジするのです。
一番最近の大絶滅は恐竜を滅ぼし白亜期を終わらせました。この原因はユカタン半島チクシュルーブに落ちた直径10〜15 kmの小惑星と考えられています。(これについては前回の記事(※1)も御覧ください。)
白亜期末以外の大絶滅はいずれも原因不明です。別の隕石が落ちたのかもしれませんし、地球規模の火山活動の活発化や酸素の減少、あるいは寒冷化によるのかもしれません。また太陽系近傍での何らかの天体爆発現象(今回のテーマ)も容疑者として挙げられています。
ここ5億年で5回の大絶滅が起きたということは、原因が何であれ、大絶滅の起きる頻度はおよそ1億年に1回といえるでしょう。
ところで地球に生命が発生したのは約35億年前と考えられています。では5億年前よりも昔にも大絶滅は起きていたのでしょうか。
最近5億年で急に地球が危険な惑星になったとも考えにくいので、それ以前にもおそらく数十回の大絶滅レベルの災害が起きていたのでしょう。しかし5億年前より昔には、多細胞生物が存在せず、大絶滅の証拠が化石から読み取れません。また岩石というものは、5億年も経つと壊されて別の岩石の原料にされてしまい、やはり昔のできごとの記録として使いにくいです。そのため5億年より昔の大絶滅については確かなことは分かりません。
(ところで30億年前の生物は、個体そのものが残っていなくても、その遺伝情報は綿綿とコピーを繰り返されて、現代まで(変容しつつも)伝わっています。遺伝情報が岩石より長持ちするのはなんだか不思議です。)