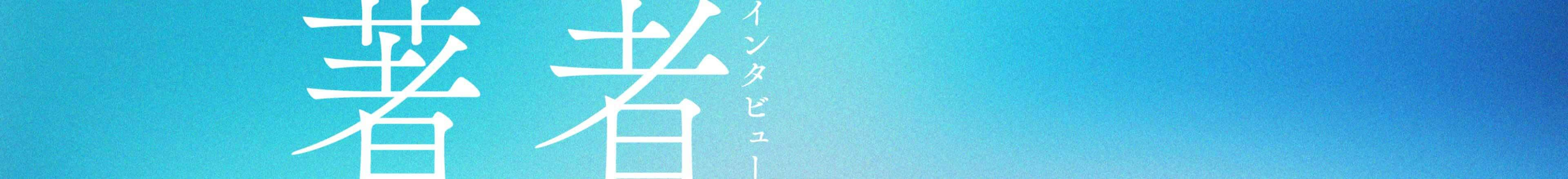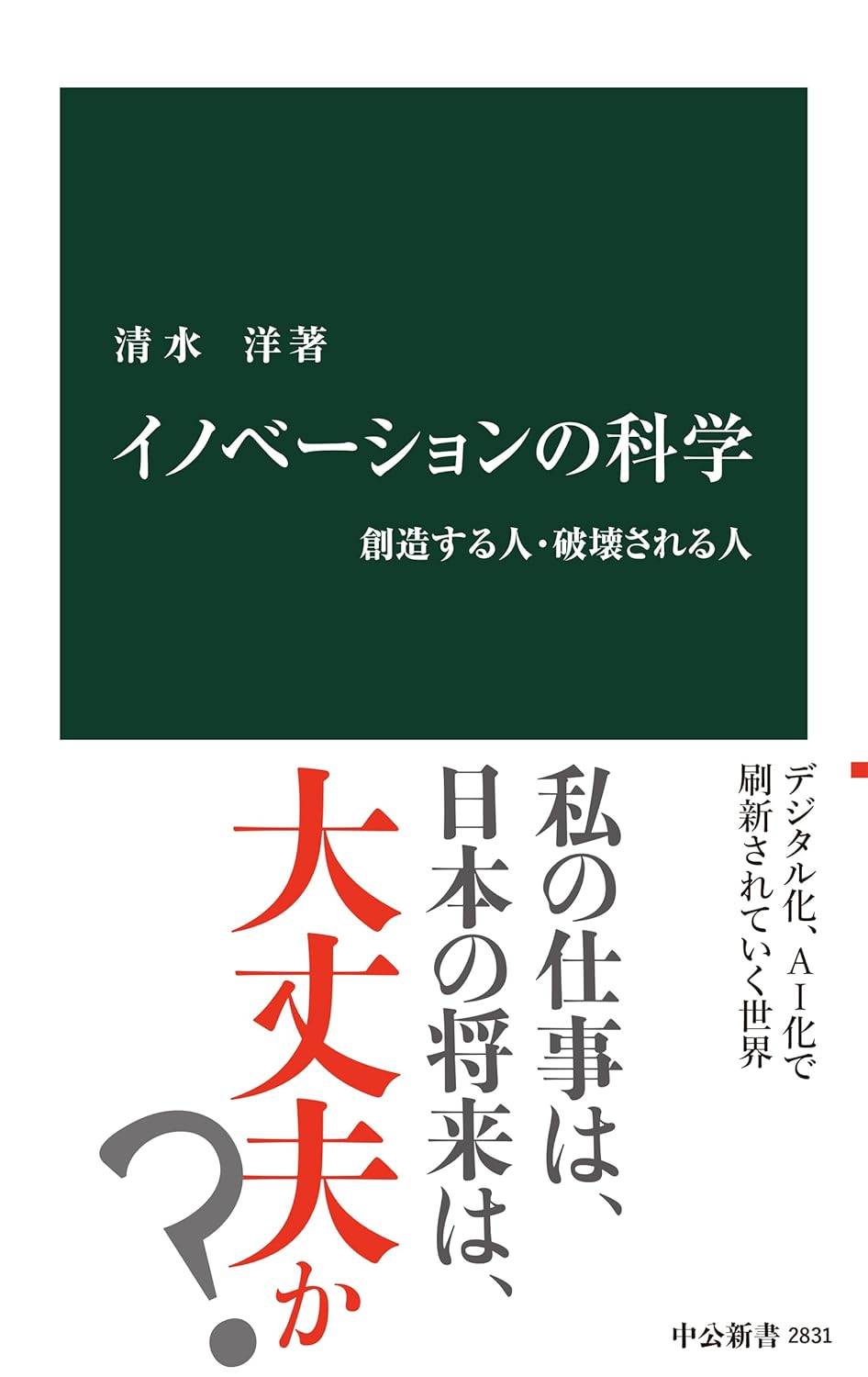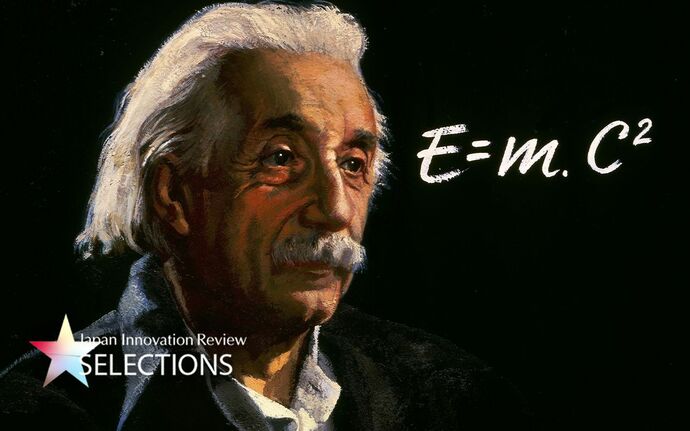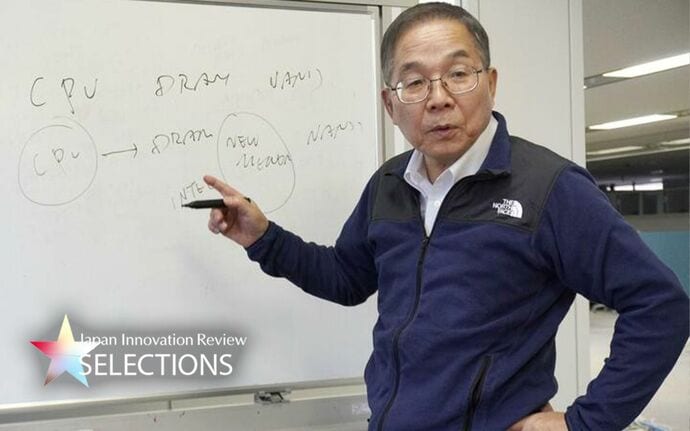出典:Adobe Stock
出典:Adobe Stock
科学技術の進化や社会変化の中で、さまざまなイノベーションが生まれている。しかし、それらを取り巻く環境は国ごとに大きく異なる。今後、日本企業がイノベーションを生み出し、社会の発展に役立てるためにはどのような考え方が必要だろうか――。2024年11月に著書『イノベーションの科学 創造する人・破壊される人』(中央公論新社)を出版した早稲田大学商学学術院教授の清水洋氏に、日本企業のビジネスリーダーが考えるべきイノベーションの在り方について聞いた。
「アメリカ型」を安易に模倣してはならない
――著書『イノベーションの科学 創造する人・破壊される人』では、世界をリードする「アメリカ型のイノベーション・システム」を模倣することに対して警鐘を鳴らしています。日本のビジネスリーダーは、このシステムの特性をどのように理解すべきでしょうか。
清水洋氏(以下敬称略) 労働者に対する保護が強い国と弱い国には、それぞれ長所と短所があるため、それを理解してイノベーションと向き合うことが大切です。
米国のように労働者の保護が弱い国は、整理解雇によって不採算ビジネスにブレーキをかけやすいため、新規性の高い研究やビジネスを生み出しやすい、という長所があります。
一方で、日本のように労働者の保護が強い国では、企業の研究開発からイノベーションが生まれやすい傾向があります。日本企業では「結果を出さないと解雇されるかもしれない」という恐怖心が少ないからこそ、社員は不確実性が高い研究開発に長期的に取り組んで成果を生み出すことができるといえるでしょう。
顕著な例として、米国のある企業のケースが挙げられます。その企業では研究開発の成果として、大きなヒットにつながるゲームが生まれました。その企業の社長が次に見せたのは、驚くべきアクションでした。