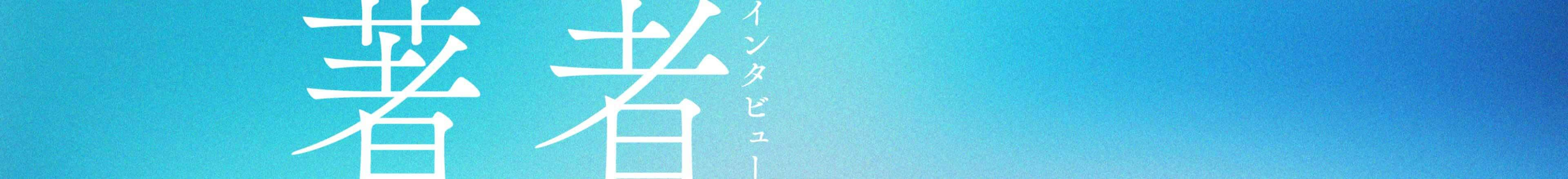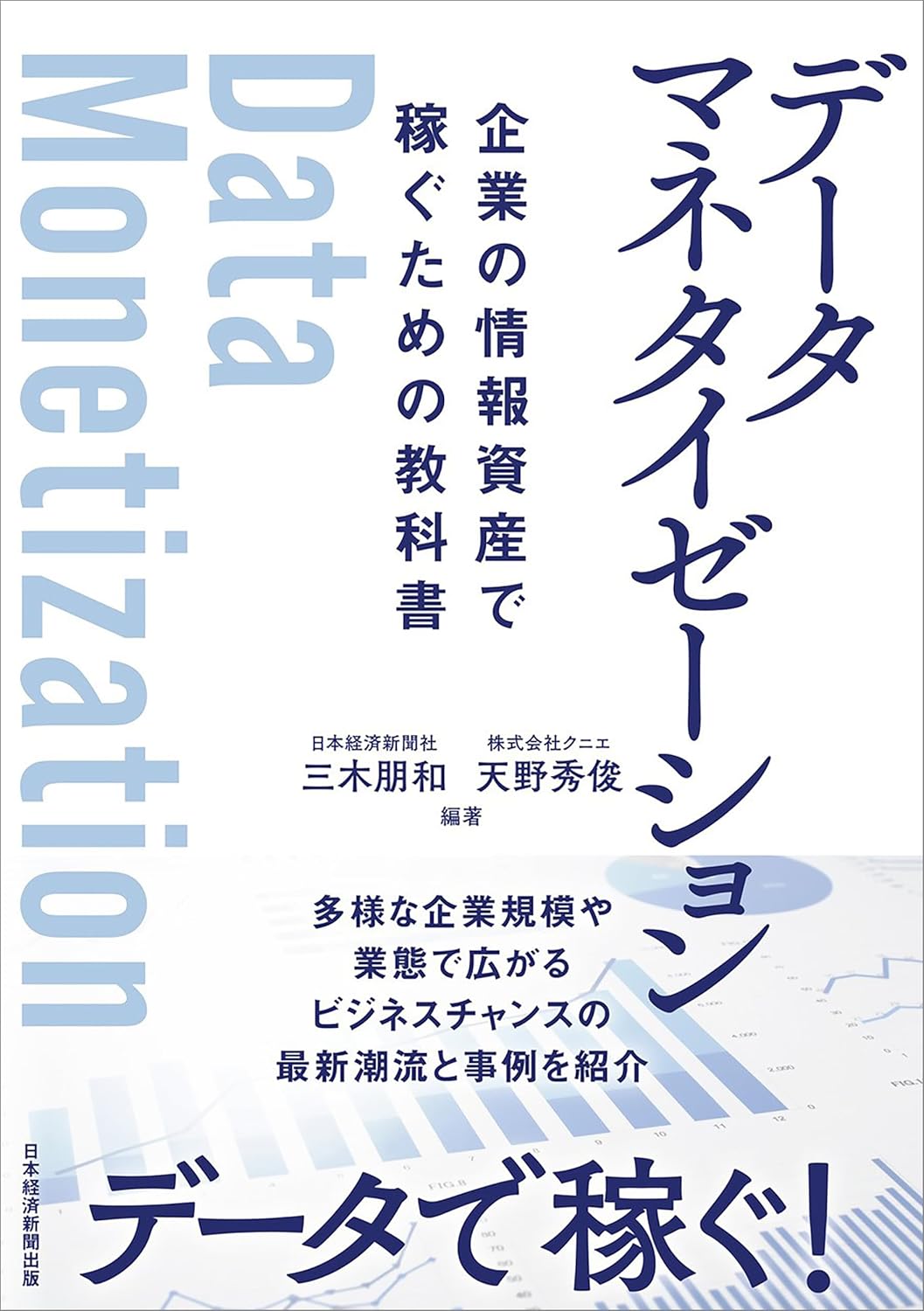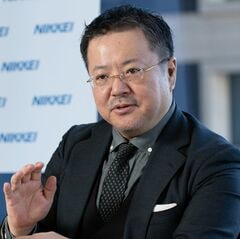出所:Joan Cros Nur Photo/共同通信イメージズ
出所:Joan Cros Nur Photo/共同通信イメージズ
社内に埋もれたデータに新たな命を吹き込み、企業の成長や新規事業開発に利活用する「データマネタイゼーション」。各社はいかにして「データで稼ぐ」取り組みを実践しているのか。2024年11月に書籍『データマネタイゼーション 企業の情報資産で稼ぐための教科書』を出版した日本経済新聞社 情報サービスユニット 上席担当部長の三木朋和氏と、クニエ 新規事業戦略チーム シニアマネージャの天野秀俊氏に、データマネタイゼーションの最新潮流と取り組み事例について聞いた。(所属・肩書は取材時点のものです)
業界プラットフォームの参画企業に求められる「協調」と「競争」
──著書『データマネタイゼーション 企業の情報資産で稼ぐための教科書』では、データマネタイゼーションを新規事業とする場合のアプローチについて解説しています。具体的にどのようなビジネスモデルがあるのでしょうか。
天野秀俊氏(以下敬称略) データマネタイゼーションのビジネスモデルには「データプラットフォームモデル」「データマーケットプレイスモデル」「ソリューションモデル」の3つがあります。
1つ目の「データプラットフォームモデル」は、いわゆる「業界プラットフォーム」と呼ばれるものです。業界の複数企業が集まり、各社のデータを出し合い融通・連携させることにより、業界全体として新しい価値を創出する取り組みです。
日本国内の事例としては、農業分野では、気象や農地、収量予測など農業に役立つデータやプログラムを組み合わせて提供することで、農業の生産性向上を目指す「WAGRI」や、医療・ヘルスケア分野でレセプトデータや健診データを取得・蓄積し、個人を特定できないように加工した上で健康情報を健康保険組合や製薬会社などに提供している「JMDC」などがあります。これらは企業や業界を越えたデータ連携の新しい取り組みであり、市場からも期待が集まっています。
ただし、実際にプラットフォームに参画するとなると、各企業にとっては「収益をどう配分するか」「成果指標をどう設定するか」など、それまでの自社のビジネス論理だけでは進めることができない部分も出てくるため、社内では総論賛成・各論反対に陥りがちです。
特に競合他社が加わった場合は、従来の市場競争とは異なる視点が求められます。こうした場合には、「協調」と「競争」を明確に分け、まずはお互いに協調できる領域から取り組むことが大切です。
例えば、欧州自動車業界のデータ連携基盤「カテナX」では、環境規制を乗り越えるために各社が協調しやすい「車載バッテリーのカーボンフットプリント *1 のデータを共有・連携」から取り組みを本格化させています。
*1. 製品やサービスの原材料調達から廃棄、リサイクルに至るまでのライフサイクル全体で排出される温室効果ガスの量をCO₂に換算した数値。