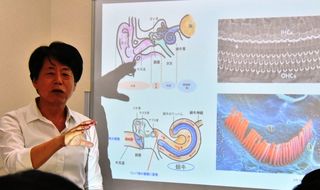光冨:免疫チェックポイント阻害剤は、いろいろな種類のがん治療において大きな成果を上げつつあります。肺がん治療においては、「これまでの抗がん剤治療に比べて、生存が有意に延長する」というデータも2015年ころから出てきています。特に昨年(2016)は、PD-L1の高発現の肺がんで、プラチナ二剤(プラチナ製剤+その他の抗がん剤の併用)の治療に比べ、明らかに寿命が延びるという発表もされました。
そのように、近年の肺がん治療は目覚ましく進歩しているため、通常は毎年改訂している「肺がん診療ガイドライン」を、数ヶ月ごとに改訂しなければならないほどの状況です。
柳澤:肺がん治療の進歩から目が離せませんね。実際に患者さんを治療するにあたり、「分子標的薬」と「免疫チェックポイント阻害剤」のどちらを選択するかは、どのように決められるのでしょうか。
光冨:まず、EGFRの遺伝子異常を調べ、それがあれば分子標的薬を使います。もし遺伝子異常が見つからなければ、免疫チェックポイント阻害剤が効きそうかどうかを調べます。
というのも、免疫チェックポイント阻害剤は、残念ながら誰にでも効果があるわけではないんです。患者さんのうち、2割程度の人に効果があるとされています。
その2割をどのように見分けるかとして、現在一番期待されているものは、「PD-L1を染色してみる」という方法です。しかしそれも、“染まる人は効きやすい”と予想されますが、“絶対に効く”のではありません。
柳澤:今のところ、まだたくさんの課題があるとはいえ、個々の患者さんの遺伝子を調べて治療ができるようになってきていることは非常に大きな進歩ですよね。現在も研究が続けられている治療法ですし、これからもっと多くの患者さんに効くようになっていくことを期待しています。