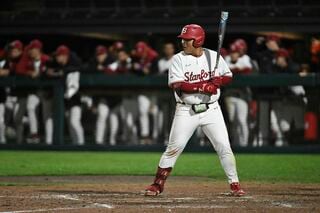そして今まさに社会として優先して取り組むべきは、予防原則に則った正しい判断を下すことではないでしょうか? 心情的には考えたくはないことであっても、蓋然(がいぜん)性が十分あると思われるリスクに対して、積極的に対応するということです。
「放射線被ばくを原因とする、健康被害が今生じている」と仮定し、今隠れているリスク、今後起こるかもしれないリスクを想定して、起こりうる危機に備えることこそが、今社会が判断して実行すべきことと思います。
チェルノブイリの経験から、たとえば小児甲状腺がん発症者数の今後の推移としては、十年後あたりにピークをむかえるまで増え続けることが予想されます(図1参照)。
福島県県民健康調査は、受診者が20歳になるまでは2年ごと、これ以降は5年ごとの検査が継続的に行われることになっています。しかしすでに受診率の低下が問題になっています。1巡目検査では全体の受診率こそ8割の高さでした。
ところが、事故当時16-18歳の年齢層の受診率は、1巡目検査では約半分、そして2巡目検査では、さらに低下して26%になっています*6。受診者にとっては、検診を受け続けることは心身ともに負担を伴うものです。今後の受診率の低下を防ぐ手だてが必要です。
また甲状腺がん検査対象年齢を事故時18歳以下の子どもだけでなく、大人にも拡大すべきという声もあります*50,51。チェルノブイリ事故後の甲状腺がん発症率の増加は、事故時18歳以上の年代にも見られているからです*52。
さらに、甲状腺以外のがんや、その他の疾患の増加も懸念されます。いま何が起きているのか、より詳細に理解するためには、健康実態調査を福島県だけでなく、放射性物質が大気にのって流れていった他県でも実施することや、住民の健康実態や疾病症例データの集約と分析を担う機関を立ち上げるなど、すべきことは少なくありません*40,43。
国際環境疫学学会からも、被ばくしたすべての住民に対し、早期発見と早期治療を可能にするための、体系的・継続的な検査の必要性を訴える提案が日本政府に対して行われています*53。
そして、甲状腺がんの多発予測が現実となったとき、医療機関がしっかりと対応できるよう、設備面や人材面での準備を行うことが求められています。また、患者さんの「生活の質」が保てるような対策や、医療費補助の体制づくりの必要性も訴えられています*54。
仮に甲状腺がんが命に関わるものでなかったとしても、成長過程にある子どもの甲状腺を手術することにより、後にどのような影響が出る可能性があるのか? これについても決して軽視することはできません。手術に伴う通常のリスク(感染、麻酔事故、甲状腺の場合は神経麻痺)や社会生活への影響、がんと診断されることへの精神的な負担なども無視できないでしょう。
個人としても、甲状腺がんを触診で見つけるための自己診断の方法*50を学ぶなど、できることはいくつかあるかもしれません。
今得られるデータと科学的な考察から予測される事態を見据えて、社会として、そして個人として、いま何をなすべきなのか。その選択のための対話の重要性がますます高まっています。
【訂正】誤った表現があったため、10章の一部内容を削除いたしました。お詫びして訂正いたします。(2016年5月13日)
(次頁は参考文献一覧)