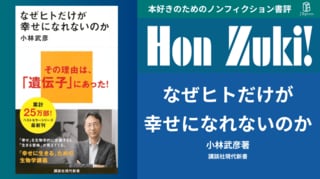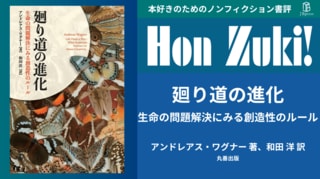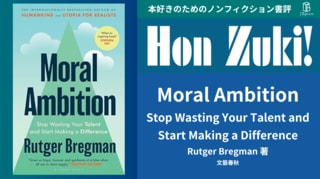遺伝学的な情報を「知らないでいる権利」
「病的な遺伝子変異を持つとはどういうこと?」と題されているのが第二章である。遺伝子検査をあまり考えずに受けられたが、それはあまりよろしくない。遺伝子検査なしではHBOCの診断など不可能だし、遺伝子レベルで病気を詳しく知ることは治療において大事である。
しかし、遺伝子検査の結果は自分だけに留まらない。もし変異があれば、親、子ども、兄弟姉妹が50%の割合で同じ遺伝子変異を持つからだ。検査をして陽性であっても自分の心中だけに留めておけばいいと思われるかもしれないが、そうはいくまい。
「生命倫理学では遺伝学的情報を知らされたくないという人は、『知らないでいる権利』を持つと考えられ、そうした権利がどんなものかが研究されている」。これは生命倫理学的にどうこう以前に、しごく当然の権利だろう。知りたくない派の人が、遺伝子変異を50%の確率で持っていると知らされってしまうというのは、どういう意味合いになるのか。なかなかに難しい。
遺伝性がんの変異を子どもに引き継がせるか、否か
遺伝性がんの変異を持っていることが、その人の結婚や生活に如何なる影響を与えるのか。これは個人によって考え方が違って当然だ。リアリティーを持ってというのは難しいかもしれないが、いちど考えてみられてはどうだろう。少なくとも、遺伝子検査を受けるつもりの人は、その前にこういったことを考えておく必要がある。
PGT-M(Preimplantation Genetic Testing for Monogenic disorders or single gene deletions:単一遺伝子疾患に対する着床前診断)という聞き慣れない検査についてが、第三章「遺伝性がんでも子どもが欲しい。『着床前遺伝学検査』という選択肢」である。子どもが欲しい、より正しくは、自分が有する遺伝子変異を持たない子どもが欲しい。そんな時、体外での人工授精によって得られた初期胚を、当該変異-HBOCの場合は当然BRCA遺伝子の変異-を持たないことを確認して着床させることができるようになっている。
日本では倫理的な観点からPGT-Mのハードルは非常に高い。日本産科婦人科学会にPGT-Mの申請をすることは可能だが、時間、資金、労力がかかりすぎる。もうひとつの方法は「生殖ツーリズム」を利用することである。日本でおこなうのが難しい生殖医療を外国でおこなうのが生殖ツーリズムで、代理出産などがそれにあたる。
著者は考え抜いた末に生殖ツーリズムを利用されるだが、そのメリット・デメリット、HBOC以外の遺伝性がんの場合はどうか、「わたしが着床前診断をしないで済む状況」の考察、さらには「『混合診療の禁止』という日本の罠」にまで話は進む。「現状の制度に不満を抱く当事者として何ができるか」という立場から書かれた内容は非常に説得力のあるものだ。