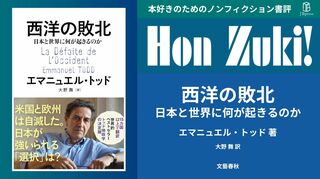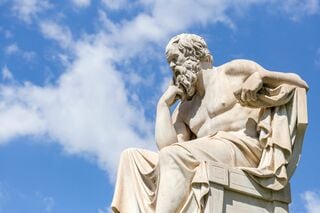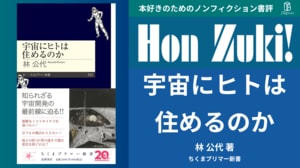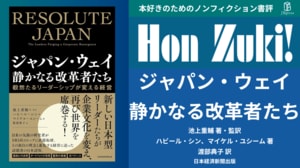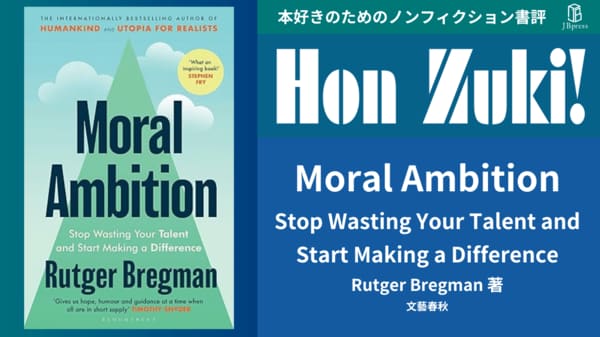
ルドガー・ブレグマン氏の新著『Moral Ambition』(未邦訳)を手に取ると、表紙にある「HOW TO STOP WASTING YOUR TALENT AND START MAKING A DIFFERENCE」(あなたの才能の無駄遣いをやめ、変化をもたらし始めるには)というメッセージが目に飛び込んでくる。
前著『Humankind』でブレグマン氏は「人間は本質的に善良である」という人間観を提示した。前著に包容力のある温かな眼差しを感じた読者は、最新作に少し驚くかもしれない。今回はより攻撃的で戦略的な視点を打ち出しているからだ。
「道徳的野心」という新しい概念
本書の核心にあるのは、「道徳的野心」(Moral Ambition)という概念である。これは、個人的な成功や富を追求する従来の「野心」とは異なり、世界をより良くするための強い意志と行動力を指す。
ブレグマンは、人のキャリアや活動を「野心的か」「理想主義的か」という2つの軸で4象限に分類するモデルを提示する。一般的に、高い社会的地位や経済的成功を目指す「野心」と、環境保護や弱者救済を通じてより良い社会を目指す「理想主義」は、トレードオフの関係にあると考えられがちだ。
しかしブレグマンは、歴史を振り返ると、実際に社会を変えてきたのは高い理想を掲げつつ野心的に行動する、つまり「道徳的野心」を持つ人々であったと指摘する。
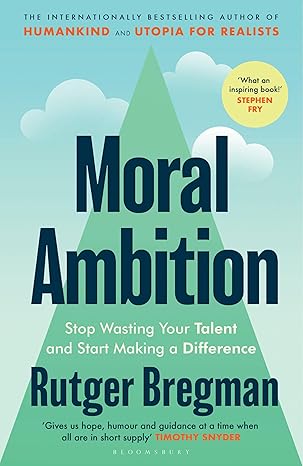 『Moral Ambition: Stop Wasting Your Talent and Start Making a Difference』Rutger Bregman著、Bloomsbury Publishing PLC
『Moral Ambition: Stop Wasting Your Talent and Start Making a Difference』Rutger Bregman著、Bloomsbury Publishing PLC
一方で、社会課題に関心を寄せる多くの「活動家」に対し、ブレグマンは手厳しい評価を下している。気候変動や貧困といった大きな課題に関心はあるものの、具体的な行動や結果よりも「問題意識」や「善意」を重視し、野心に欠ける理想主義者が多いというのだ。彼らは言葉や意図を重んじるあまり、行動や結果を伴わず、具体的な成果は乏しいとブレグマンは指摘する。
優しさや正義感だけでは足りない。世界を変えるには「道徳的野心」が必要なのだ。
戦略性としたたかさの重要性
本書で繰り返し語られるのは、社会変革には「戦略的な動き」や「したたかさ」が必要だということである。その象徴的な事例として、公民権運動のローザ・パークスが詳しく取り上げられている。
多くの人が知るローザ・パークスの物語は、疲れてバスに乗った「善良なお針子さん」が白人用の席から立つことを拒否したという美談だ。しかし真実はもっと重層的である。パークスは一般人ではなく、活動家のためのハイランダー民俗学校で抗議戦術のワークショップを受講した経験豊富な公民権活動家だった。
さらに重要なのは、この出来事が偶発的なものではなかったことである。女性政治評議会(WPC)という団体が何ヶ月も前からバス・ボイコットを計画し、「適切な瞬間」を探していた。パークスが逮捕されると、WPCは逮捕当夜に35,000枚のビラを印刷し、翌朝20人の女性が市の全域に配布した。マーティン・ルーサー・キング・ジュニアを含む男性教会指導者たちの参加は、その後のことだった。
パークス自身も「控えめなヒロイン」という役割を意図的に演じ、自身の活動歴を曖昧にする戦略を採った。現在でも多くの人が彼女を「善良なお針子さん」だと思っているのは、この戦略が成功した証拠と言えるだろう。
ピル開発に見る戦略的投資
「戦略的な動き」のもう一つの事例として、避妊用ピルの開発が挙げられる。この革新的な発明の背景には、キャサリン・マコーミックという女性の存在があった。1904年にMITを卒業した史上2人目の女性である彼女は、女性の避妊の権利のために活動していた。
1947年、70代になった彼女は夫の遺産を相続し、安全で確実で安価な避妊具を開発できる人物を探し始めた。知人を通じて出会ったのが、性や生殖に関する研究でハーバード大学を解雇された生物学者グレゴリー・グッドウィン・ピンカス博士だった。
マコーミックは彼に会うとすぐに支援を決め、ピンカス博士の研究に200万ドル以上の私財を投じた。その数年後、ピンカス博士が発見した「エノビッド」がFDAに承認され、単に「ピル」として知られるようになった。何百万もの女性が自分自身の体をコントロールできるようになったのだ。
マコーミックは多くの富裕層が行う「周囲から承認を得やすい慈善活動」とは異なり、当時の価値観ではタブー視されていた課題と問題ある人物を支援した。自分の才能と財産を戦略的に使い、先端的な研究と道徳的野心を結びつけて歴史的インパクトを生み出した実例である。