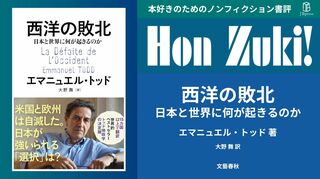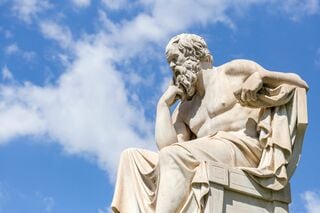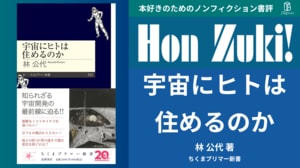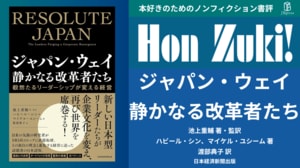行動への敷居を下げる仕組み
本書が強調するもう一つの重要な点は、「行動への敷居を下げる」ことだ。道徳的野心は直情的な正義感でも特別な能力でもなく、普通の人の間に伝染するものだとブレグマンは指摘している。
例えば、ホロコースト中にユダヤ人を匿った人々の研究では興味深い事実が浮かび上がっている。彼らに共通する特徴は、特別な性質や志向ではなく、「頼まれたから」という状況だった。困っている人がいる、助けてほしいと頼まれた人のほぼ全員が「分かった」と了承し、支援の輪が広がったのだ。
つまり重要なのは、個人的な特性よりも、外部からの「声かけ」や「頼まれること」が道徳的野心のきっかけとなることなのである。
さらに、道徳的野心に基づく行動は学んで身につけることができるとブレグマンは説く。その実例として、ロンドンにあるCharity Entrepreneurshipが紹介されている。この組織は、世界を変える非営利団体のインキュベーションプログラムを運営している。
重要な特徴が2つある。1つ目は、取り組むべき社会課題をCharity Entrepreneurship側が科学的に調査して用意していることだ。その条件をブレグマンは3つの「S」にまとめている。
Sizeable(規模が大きい):その問題が広範囲に影響を与えること
Super-solvable(解決可能である):解決策が存在するか、解決に向けた明確な道筋があること
Sorely overlooked(見過ごされている):問題の規模や解決可能性にもかかわらず、現状では十分な関心やリソースが向けられていないこと
つまり、参加者が「何をしたいか」ではなく「結果が出るか」が重視される。その結果、プログラム参加者の多くは、それ以前には想定していなかった領域で活動を創設するそうだ。
2つ目の特徴は、才能はあるものの自分の力を過小評価している人々に「あなたにはやるべき使命がある」と伝える「賢い老ウィザード」の役割を果たすことだ。ハリー・ポッターが魔法使いへの道を自分から探したのではなく、ホグワーツの先生がハリーに入学を働きかけてくれたように、道徳的野心は「伝染する心の持ち方」なのである。社会課題解決にインパクトを出すのは才能ではない、マインドセットであるとブレグマンは述べている。そのようなマインドセットを育むのは、環境なのだ。