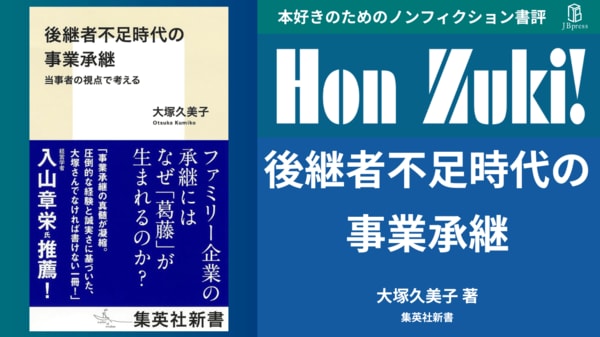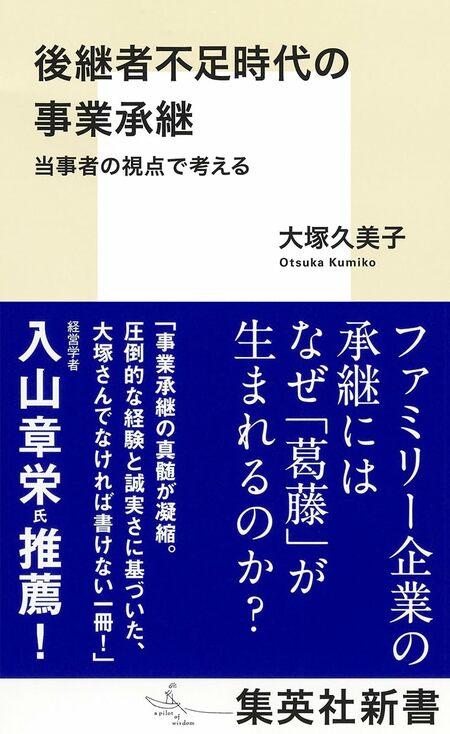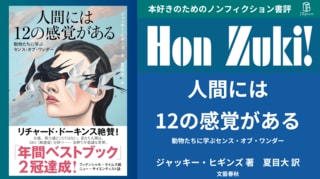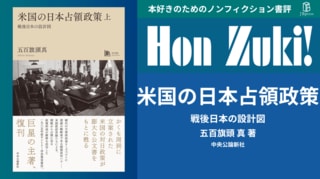大塚家具のプロキシーファイト(委任状争奪戦)の「騒動」を記憶している人も多いだろう。
著者である大塚久美子氏ら会社側が勝利を収めたものの、組織は分断され、現場は疲弊した。そしてその後、紆余曲折を経て大塚家具は会社としては消滅し、ヤマダ電機に吸収されることとなった。
本書は、事業承継に潜む葛藤とその解決について、その当事者が様々な観点から考察したものだ。
「騒動」の事後に、当事者によって書かれた本は、ややもすると言い訳めいていたり、自己主張に終わるものも少なくないが、本著は、個人的な体験を客観的に分析し、構造問題として昇華させ、同様の課題に悩んでいるであろう読者への処方箋たらんとして誠実に書かれている。
経営学者入山章栄氏が「事業承継の真髄が凝縮。圧倒的な経験と誠実さに基づいた、大塚さんでなければ書けない一冊!」と激賞する様に、会社とは誰のものか...株主とは...ガバナンスとは...M&Aとは、といったテーマをカバーする経営の実践書として、極めて完成度が高い。
しかし、本書は実践の書であると同時に、日本社会の宿痾を抉り出す生々しいドキュメンタリーでもあり、かつ人生に悩む多くの人々にとっての生き方の指南書でもある。
オールドメディアと大衆のナラティブが生んだ「騒動」
まず描かれているのは、この「騒動」に至った経緯と背景、メディア報道の「事実誤認」と人々のナラティブの問題だ。
「後継社長の低価格路線シフト戦略のミス」、あるいは面白おかしい「親子喧嘩」。当時そのような報道があふれ、今なお多くの人の記憶に焼き付いているのは、そうしたイメージだろう。かくいう私も、原因は戦略の路線対立を巡るものもあるのだろうと、まさに誤認していた。
しかし実態は異なり、それらは当時のIRコンサルタントが、株主からの委任状を争奪するための「奇策」としてメディアを利用して作り上げたナラティブだった。
対立関係にある会長と社長が「父と娘」である構造を利用し、プロキシーファイトを「家庭内の不和」として印象づける。「低価格化戦略」や「接客サービスの廃止」も、会長側の印象操作に乗ったメディアによるフェイクニュースに近いものだが、いまだにそれを前提とした記事が書かれ続けている。
本当の争点は、創業の地に数十億円規模の大規模施設を建てたい創業会長と、会社にその投資余力はないと判断する後継社長の投資案件を巡る意見の相違だった。 投資を強行したい会長と、阻止すべきと考える社長、そしてその意見の相違は、徐々に様々な動機でそれを利用しようとする親族、幹部社員、社外の人間を巻き込み大きな対立構造となり、結果として、当事者が誰も望まないプロキシーファイトにまで発展した。
経営不振に陥っている近年のメディアは、読者が「知るべきこと」よりも、「知りたいこと」を優先し、分かりやすく興味を引く「分断の構造」を書きたがる。
2010年代中盤、私(評者)も、東京都の顧問として五輪予算の調査に関わっていた際、同じ状況に直面した。記者に五輪予算の背景や複雑な運営構造を説明しても、彼らのメモを取るペンは全く動かない。彼らが欲しがったのは、当時の森喜朗組織委員会会長と小池百合子新都知事との因縁と対立だけだった。「老害元総理を果敢に攻撃する女性リーダー」というナラティブが読者に受けていたからだ。
ポスト真実の時代、事実は軽視され、「親子喧嘩」や「美女と野獣」のような分かりやすいナラティブが拡散される。著者の場合、高学歴の女性社長ということもあって、「男性は女性より優れている」「女性は家庭を担うべき」といったミソジニスト(misogynist)からのネット上の攻撃も多かった様に思う。
人々は自分にとって理解しやすい方を信じ、一度信じれば、それがその人にとっての「真実」となる。「おねだり知事」「ラブホ市長」等、バズる内容であれば「騒動」として過熱報道に走るオールドメディアの体質と、それをエンタメとして消費する社会の危うさの象徴でもあったことを、この「騒動」も思い起こさせる。