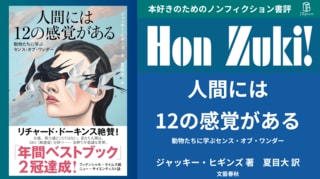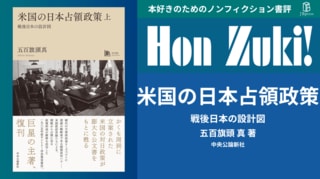日本の家族構造類型と事業承継問題
もう一つの重要な論点は、著者が自身の体験を整理し構造化し、戦後日本のファミリービジネスにおける事業承継の特殊性を明晰に分析している点だ。
著者は会社を、①一般的な「日本的経営」、②老舗のファミリー企業、そして大塚家具のような③「(戦後)昭和創業者の企業」に類型化し、それぞれの規範について考察している。
①と②は、共に、共同体としての会社と社員(②は親族含む)の利益を重視し、長期的な事業と雇用の継続を最重要課題とする点で共通している。そこには、伝統文化や皇室にも通じる「スチュワードシップ(受託者責任)」の規範が存在する。
歴史人口学者のエマニュエル・トッドによれば、日本の家族類型は「権威主義型(直系家族)」である。家督を継ぐ者が家産を独占的に相続する権利を持つ一方で、承継の義務も負う。「家」と「家業」を次世代へつなぐことが当主の責務であり、それができなければ「先祖に顔向けできない」。
ところが、③の「戦後昭和の創業者」は異なる。彼らは戦後の個人主義の思想で育ち、「家」制度の義務からいち早く自由になっている。著者の表現を借りれば、彼らは『「家」をハイジャックする個人』だ。
会社を創業した彼らにとって、会社は私的所有物であり、象徴的な意味での自分自身でもある。究極的には、一代限りで潰しても良いとさえ思っている節がある。そのため、事業承継において最も葛藤を生じやすいのが、この「戦後の創業者」からの承継なのだ。
「こうした規範(家の継続)の影響下にないのが『戦後の創業者』です。」(第1章 葛藤の構造〜「家」vs 「株式会社」より)
評者には、この後継者育成と事業承継の問題は、戦後の創業社長に共通の課題に感じられる。
NIDECの永守社長も、数年にわたる後継者問題を抱え「50年頑張ってきたが、最後の方は恥の上塗りだった」と吐露している。
ユニクロの柳井会長も「玉塚は、育ちはいいがつまらない凡人だった」等と、数々の後継候補を引き上げては潰し、以来、人に任せることに懲りたかのように、会長兼社長を20年務めている。
ソフトバンクの孫社長も、一度は引退を決めて後継者指名をしたものの「もっとやりたいという欲望が出た」「急にさみしくなった」と社長交代を撤回している。
戦後創業者からの事業承継においては、様々な「騒動」が起きているが、本書では事業承継問題を実体験した当事者によって、この問題の客観的な構造化がなされている。
ともすれば個別的、情緒的になりがちな「イエ」と「アトツギ」の問題だが、元来研究者を志望していた著者による客観的な分析によって、戦後の日本企業に普遍的な構造問題が鮮明に浮かび上がってくる。