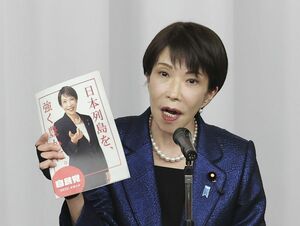ハルジオンの花とモモブトチビハナアブ(写真:筆者)
ハルジオンの花とモモブトチビハナアブ(写真:筆者)
(岸 茂樹:国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 上級研究員)
少しずつ暖かくなってきた。3月5日は二十四節気の一つ、啓蟄である。啓蟄は蟄(すごもり)を啓(ひら)く、つまり冬眠していた生物が地上に出てくるという意味がある。毎年この日をまたぐと、今年もまた昆虫たちが動き始めるな、と期待と不安が入り混じったような気分になる。
私はこれまで昆虫の研究をしてきた。京都大学大学院では食糞性コガネムシ、フン虫の子育て行動を研究した。その後、アズキゾウムシというアズキを食べる小さな貯穀害虫の研究をした後、花に来る昆虫の研究を始めた。最近ではウンカや作物病害虫の研究もしている。
専門分野は生態学で、生き物がなぜ増えたり減ったりするのかという問題を研究している。たとえば、なぜカメムシが大発生するのかという問題は生態学のど真ん中の研究テーマである。私自身は個体の行動が個体群や群集全体にどのような影響を及ぼすかという問題に興味があるのだが、国の研究機関の研究員なので、仕事ではいろいろな研究を進めている。
また、私は大学院の博士課程在学中に「ハカセ」というあだ名で「あいのり」という番組に出演した。スタッフの方とあだ名を決めるときに「フンコロガシ」「学者」と候補が挙がったが、ひょっこりひょうたん島の博士にちなんで「ハカセ」になった。もう20年以上前のことになるが、いい思い出である。
一度、研究の道からいったん距離を置いた時期もあった。2009年から2011年の間、広告代理店に2年ほど勤めたこともある。会社ではマーケティングや企画を担当した。そのときのエピソードは書籍『アカデミアを離れてみたら』(岩波書店)に書いた。
今回、機会をいただき、昆虫の研究で感じてきた自然の面白さを中心に、生態学の話をしていこうと思う。そうした研究のエッセンスをお伝えすることで、多くの方の日ごろの仕事や生活にも考えるヒントを得ていただけるのではないかと考えている。
さて、今回は花と昆虫のちょっと不思議なネットワークの話をしたいと思う。