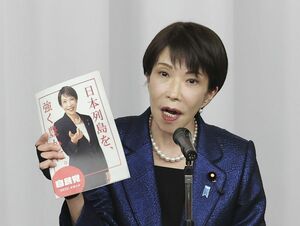26兆円超の経済価値を支える“花と昆虫”、ミツバチだけにとどまらない意外な主役たち
花と昆虫が織りなす知られざる送粉ネットワークの力、無駄なつながりを作るほどネットワークは頑丈に
岸 茂樹
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 上級研究員
2025.3.4(火)
ここからは、JBpress Premium 限定です。
カンタン登録!続けて記事をお読みください。詳細はこちら
ここからは、JBpress Premium 限定です。
カンタン登録!続けて記事をお読みください。詳細はこちら