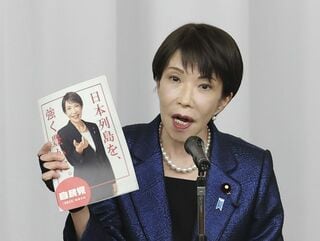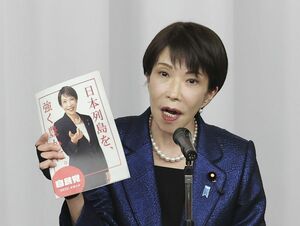アザミの蜜を吸うホシホウジャク(2020年9月、小石川植物園にて著者撮影)
アザミの蜜を吸うホシホウジャク(2020年9月、小石川植物園にて著者撮影)
(岸 茂樹:国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 上級研究員)
暑い。関東でも真夏日が続くようになった。スーパーに行くと夏を代表する野菜、ニガウリ(ゴーヤ)が店頭に並んでいる。ゴーヤチャンプルーにかつお節をたっぷりかけて食べるのが好きだ。豚肉と卵の甘みとニガウリの苦み、かつお節のうまみを口の中で楽しみながらビールを流し込む。止まらないおいしさである。
今回はニガウリの受粉と結実(けつじつ:実ができること)に関する論文が出版されたので紹介したい(Kishi et al. 2025)。ニガウリの実ができるためには昆虫が花粉を運ぶ必要があるが、ミツバチは花粉をあまり運んでくれないという問題があった。今回の研究結果は、スズメガという蛾がその問題を解決する可能性を示している。
ニガウリの受粉問題
ニガウリは雄花と雌花が別々に咲くので昆虫が雄花から雌花に花粉を運ぶ必要がある(写真1)。野外で栽培するときにはあまり問題にならないが、ハウス栽培では花粉を運ぶ昆虫が必要になる。
 ニガウリの雄花(いずれも)。雌花もよく似ているが花粉も蜜も出さない(2022年8月つくば市、著者撮影)
ニガウリの雄花(いずれも)。雌花もよく似ているが花粉も蜜も出さない(2022年8月つくば市、著者撮影)
これまではセイヨウミツバチをハウスの中に導入していたが、期待するほど花粉を運ばないことが分かってきた。なぜならニガウリの雌花は蜜を出さないのでミツバチは次第に雄花と雌花を見分けるようになり、次第に雌花を避け、雄花ばかりを選んでしまうからである。結果として雌花に花粉が付かずに実が減ってしまう問題があった。
この問題の対策として人工授粉が行われてきたが、毎日雌花を一つひとつ巡って花粉を付けていくのは大変な労力がかかる。そのため最近は花粉が付かなくても実が成る単為結実品種が使われるようになってきたが、そうした品種でも受粉することで大きく、形のよい実ができるのでミツバチに代わる送粉昆虫が待望されていた。
そこでまず私たちはニガウリの訪花昆虫を調べることにした。予想通りミツバチやマルハナバチ、小型ハナバチなどが多く訪れていたが、その中に、見慣れない昆虫がときどきやってきていることに気づいた。スズメガである。