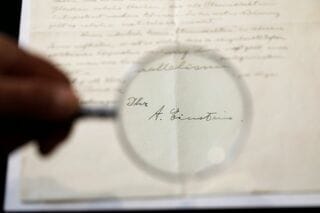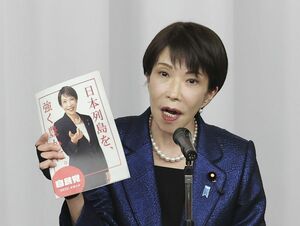クワガタムシの大顎はなぜ大きくなるのか?(写真:sora_nus/イメージマート)
クワガタムシの大顎はなぜ大きくなるのか?(写真:sora_nus/イメージマート)
クワガタムシは、その特徴的な見た目と力強さから、高い人気を誇る昆虫である。しかしながら、クワガタムシをクワガタムシたらしめているハサミ型のツノのようなものの正体が、顎の一部(大顎)であることはあまり知られていない。また、非常に特徴的な発達の仕方であるにもかかわらず、大顎の発達を決定づけるメカニズムも、完全に解明されたわけではない。
クワガタムシの大顎は、どのようなメカニズムで大型化し、カッコいいシンボルとなるのか。「クワガタ博士」として知られる後藤寛貴氏(静岡大学理学部生物科学科助教)に話を聞いた。(聞き手:関瑶子、ライター&ビデオクリエイター)
「少なくともカブトムシと一緒にしてほしくない」
──昆虫の二大巨塔と言えば、クワガタムシとカブトムシだと思います。なぜカブトムシではなく、クワガタムシを主な研究対象としているのですか。
後藤寛貴氏(以下、後藤):まずクワガタムシの魅力からお伝えすると、やはり大きく発達した顎のカッコよさでしょう。俗に「ツノ」や「ハサミ」などと呼ばれる部位ですが、あれは顎が大きく発達したものです。
研究対象としてのクワガタムシの面白さは、大顎の形態やサイズが種や個体によって大きく異なる点です。シンプルな「大顎のカタチがかっこいい!」という気持ちももちろんありますが、そのバリエーションの多さも、僕の研究意欲をかき立てます。
一方、カブトムシはと言うと、シンボルマークである角(ツノ)の形態には、それほど多様性はありません。特に日本のカブトムシだと、大きい個体でも小さい個体でもツノの形状はあまり変わりません。
また、カブトムシファンの方には大変申し訳ないのですが、僕は「下品」という言葉こそ、カブトムシを表現するのにうってつけだと思っています。
というのも、カブトムシはエサにもメスにもがっつく、ところ構わずおしっこをジャージャーする。見境ないと言いますか、ガツガツしている。
それに比べると、クワガタはとても繊細で上品と言えるかと思います。少なくともカブトムシと一緒にしてほしくはないです。
──クワガタムシの大顎は、なぜそれほど多様性があるのですか。