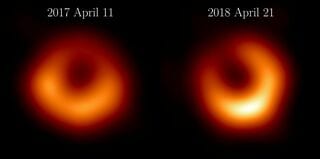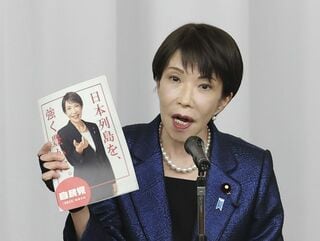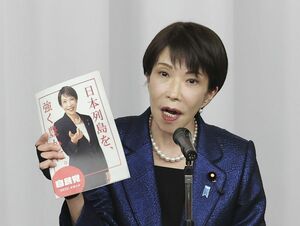芋煮をはじめ、山形には地域ごとに多様な食文化がある(写真:共同通信社)
芋煮をはじめ、山形には地域ごとに多様な食文化がある(写真:共同通信社)
慶應義塾大学先端生命科学研究所(以下、慶應先端研)は、山形県鶴岡市にある。前回記事「世界に直接つながる知られざる研究都市、慶應義塾大学が日本海沿いの山形・鶴岡に拠点を置く理由」で書いたように、メタボロームという特化した分野で国際的な地位を確立し、世界から研究者を引きつけている。これは一つの奇跡に見えたかもしれないが、これは日本のどこだろうが、その場を変えようと思う人がいるならば、実現できると思う。
鶴岡市は、日本で初めて「ユネスコ食文化創造都市」に登録された。この食という側面からも、鶴岡市は研究都市を発展させようとしている。今回は、鶴岡市が取り組む「食と科学」に関連した動きを見ていきたい。
バイオ技術でワインの飲み頃が分かる
今年、鶴岡市の「鶴岡ガストロノミック・イノベーション計画」が、内閣府の「地方大学・地域産業創成交付金事業」に採択された。この計画では、今後10年間で「食を科学する研究拠点」を鶴岡市に整備し、そこで生まれる新たな食材や技術を活用して地域産業を育てることを目指している。
元来、鶴岡市では、食の科学に関連した研究機関が整備されてきた。
鶴岡市には「庄内地域産業振興センター」がある。ここを中心に、慶應先端研や地元の企業も関係しながら、「バイオクラスター形成促進事業」というプロジェクトに取り組んでいる。経済産業省などが進めるバイオクラスターは有名な取り組みだが、鶴岡市が注目した分野の一つが「バイオ×食」である。
このプロジェクトでは、食べ物などさまざまな製品の成分を詳しく調べるのだが、ここでも慶應先端研が得意とする「メタボローム解析」という最新の技術が駆使されている。
この解析の技術を用いて行われているのが、ワインなどのお酒を作る過程で成分がどう変化するかを詳しく調べ、味との関係を探る研究だ。例えば、ワインの飲み頃がデータで分かるようになり、誰でも客観的に「一番おいしい時期」が分かるようになることが期待されている。
 メタボローム解析で解析されたワイン(写真:著者)
メタボローム解析で解析されたワイン(写真:著者)
 バイオクラスターで製品化された商品(写真:著者)
バイオクラスターで製品化された商品(写真:著者)
こういった技術を利用することで、食品に含まれる新しい有効成分の発見にもつながっている。
食べ物の成分を正確に、しかも幅広く調べられるようになったことで、これまで職人の経験や勘に頼っていた作業や代々受け継がれてきた特別な技術も、食品の成分をデータとして記録し、客観的に評価できるようになる。その結果、技術を次の世代に伝えやすくなり、作る食品の品質を安定させることにもつながる。
話を戻すと、鶴岡ガストロノミック・イノベーション計画の推進に当たって鍵になるのが農学部だ。
慶應大学には食に大きく関わる学問領域を専攻する農学部が存在しない。そこで、山形大学農学部と連携することにより、不足の学問領域を補完しようとしている。鶴岡市にある慶應先端研と山形大学農学部が連携し、研究開発が進められる予定だ。
農学部を核に、慶應大学と山形大学が食文化や食材に着目し、科学の観点から農の世界を広げていくという未来である。