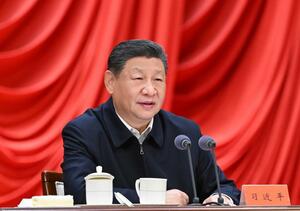(英エコノミスト誌 2024年4月6日号)
 日本製鉄によるUSスチール(写真)買収提案は日米間に新たな摩擦を生じさせている(2024年2月資料写真、写真:AP/アフロ)
日本製鉄によるUSスチール(写真)買収提案は日米間に新たな摩擦を生じさせている(2024年2月資料写真、写真:AP/アフロ)
資本主義の総本山が保護主義に傾くなか、日本は開放を進めている。
第2次世界大戦後の日米関係において最も背筋が寒くなる事件の一つが1982年に起きた。場所は米国のデトロイトだ。
米国人の雇用を盗み取っているとして日本人を非難していた米国人の自動車工場労働者2人が、ある中国系米国人の男性を日本人と勘違いして野球のバットで殴り殺した。
加害者に同情した判事は2人に3000ドルの罰金を科しただけで、刑務所には送らなかった。
このとてつもなく寛大な判決は、後に政府のトップレベルにまで伝わった当時のムードを反映していた。
世界の経済的超大国の座を日本に奪われることを恐れた米国は、バールを手に取り、振り回した。
貿易規制を導入し、日本の国内市場をこじあけようと試み、為替レートを円高ドル安に調整する国際的な取り組みを主導した。
米国がその手を緩めたのは、1990年代に入って日本の資産価格バブルが崩壊した後のことだった。
思わぬ逆転現象
日本製鉄が米USスチールを150億ドルで買収する計画を発表したことを受け、超党派の議員が米国の雇用を守るとの理由から買収計画を阻止しようとしている直近の取り組みを含め、米国で新たに始まった保護主義の発作に日本人が既視感を覚えるのではないかと思う人もいるかもしれない。
だが、話はもっと複雑だ。
世界で最も重要な戦略的パートナーシップの一つである日米関係では近年、予期しなかった変化が生じている。
長らく米国が手がけてきた株主重視・市場重視の改革を日本が進める一方、かつて日本の十八番だった産業政策や保護主義の類いを米国が導入しているのだ。
この逆転現象は、米国が国内でビジネスの自給自足を追求する一方、中国に対抗すべくグローバルな同盟関係を構築しようとしているために直面する様々な矛盾について、多くのことを明らかにしている。
日本のアプローチの方が理にかなっている。
筆者は2010年代の初めに日本に住んでいたが、それからわずか10年間で成し遂げられた変化には目を見張るものがある。
金利の上昇や株高といった大局的なことだけではない。
人口減少による経済の向かい風を相殺しようと奮闘するなか、草の根レベルでも変化が見られる。楽観的な見解の持ち主に話を聞けば、失われた数十年の特徴がいくつか視界から消えていることに気づくだろう。