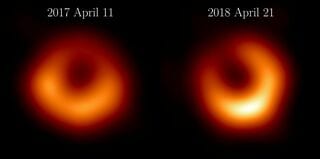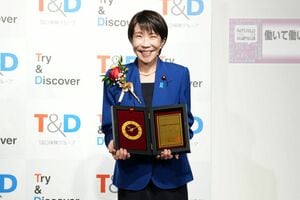「税金でエリート養成」という批判をいかにして乗り越えたか
小林:ほかにも、1967年に都立高校が学校群制度を導入したことも、筑駒に有利に働きました。学校群制度は、地域内にいくつかの学校(群)のグループ編成をつくり、受験生は希望する高校が属する群に出願するというものです。
合格者は、出願した群内の高校に振り分けられるため、いくら勉強ができても希望する高校に進学できるとは限りません。
そこで、日比谷高校などの都立トップ校を目指すレベルの生徒たちの都立高校離れが始まります。麻布や武蔵(※)、開成、そして国立の筑駒を目指すようになりました。(※当時は麻布、武蔵ともに、高校から生徒募集を行っていた)
これも筑駒を進学校にしてしまった大きな要因の一つです。
──「進学校にしてしまった」とは、どういうことでしょうか。
小林:私立の学校は自ら望んで進学校になろうとします。でも、筑駒は偶然が重なった結果、優秀な子が集まるようになり「進学校になった」ということです。
 いつの間にか日本屈指の進学校になってしまった筑駒(写真:No machine-readable author provided. Benjamin58 assumed (based on copyright claims)., CC BY-SA 3.0
いつの間にか日本屈指の進学校になってしまった筑駒(写真:No machine-readable author provided. Benjamin58 assumed (based on copyright claims)., CC BY-SA 3.0 生徒が優秀すぎるがゆえ、授業も独特で高度なものが展開されます。そして、東大進学率が高い。でも、筑駒は、国立大の附属校であり、税金によって運営されています。1960年代から80年代は、エリート批判が強かった時代です。税金でエリート養成機関をつくるのはいかがなものかという反発があり、筑駒が叩かれることになったのです。
民主党政権のときには、筑駒をはじめとする国立大の附属校は仕分けの対象となりました。特に、エリート養成機関と見なされていた筑駒に対する風当たりは相当なものでした。下手をすれば民営化や大学から切り離されるという事態にまで追い込まれます。その頃の職員会議は、いつも緊張に包まれていたそうです。
──そういった批判に対し、筑駒側はどのように対応したのでしょうか。
小林:「エリート養成」と言うと、国民はあまり良い印象は受けないでしょう。そこで、筑駒は「リーダー養成」という言葉を打ち出しました。国や社会、企業を引っ張っていく人材を育成する教育機関であるとアピールしたのです。
また、筑駒は2002年からスーパーサイエンスハイスクール(SSH)の指定校となりました。SSHは、文部科学省がサイエンス系の教育を重点的に行う高校を指定する制度です。
この制度のもと、筑駒は筑波大学の研究室訪問など、高大連携を深めていきます。SSHでは、高校の学習指導要領をはるかに超えた、大学、大学院レベルの専門性の高い教養に触れることができます。
このわかりやすい成果として、筑駒は国際科学オリンピックや国際数学オリンピックの常連校となりました。メダル獲得者も多く輩出しています。
リーダー養成を打ち出したこと、SSH指定校としてサイエンス教育に力を入れ成果を出したこと。これにより、筑駒は苦境を乗り越えることができたのです。