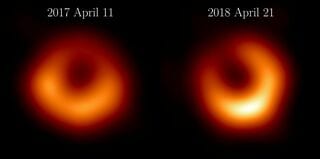メロンを売るロヒンギャの女の子(写真:ZUMAPRESS/アフロ)
メロンを売るロヒンギャの女の子(写真:ZUMAPRESS/アフロ)
世界は難民で溢れている。国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)によると、2022年末時点で紛争や迫害などにより故郷を追われた難民は1億人を超える。
難民と聞くと、シリアやウクライナ、そしてガザ地区といった西アジアや中東を思い浮かべる人が多いだろう。しかし、日本からそう遠くない東南アジアにも難民がいる。そのうちの一つが、ミャンマーの「ロヒンギャ」と呼ばれる人々だ。
3年前の2021年2月、ミャンマーで軍事クーデターが発生したことは日本人の記憶にも新しい。なぜロヒンギャは難民となったのか、軍事クーデターとロヒンギャ難民に関係はあるのか、今後ロヒンギャは祖国に帰還できるのか──。ミャンマー/ビルマ政治史を研究する長田紀之氏(独立行政法人日本貿易振興機構 アジア経済研究所 研究員)に話を聞いた。(聞き手:関瑶子、ライター&ビデオクリエイター)
──ミャンマーは、人口の約70%がビルマ族ですが、他にカチン族、カヤー族など、130を超える民族を抱える多民族国家です。その中で、なぜ「ロヒンギャ」が迫害対象となっているのでしょうか。
長田紀之氏(以下、長田):ロヒンギャの問題を考える前に、まずはミャンマーの歴史を知る必要があります。
数多くの少数民族のなかでのロヒンギャの特殊性は、土着の民族とみなされず、そのために国民とみなされてこなかったところにあります。それは、ミャンマーが近代国家として形成されてきた経緯とも深く関わります。
現在のミャンマーの国境線は、19世紀から20世紀にかけてのイギリス植民地時代におおむねかたちづくられました。このとき、ミャンマーは、現在のインド、バングラデシュ、パキスタンを含む英領インドという枠組みに組み込まれるかたちで、イギリスの植民地となりました。この植民地時代に、中国やタイとの間に厳密な国境線が引かれていったのです。
英領インド内のミャンマーでは、イギリスにより様々な経済開発が行われました。そのとき、膨大な人口を抱えたインド亜大陸から、多くの労働人口が流入しました。こうした移民の一部は経済的に成功し、ミャンマー経済の重要な部分を占めるようになります。
つまり、イギリス植民地時代のミャンマーでは、イギリスが行政を支配し、インド系の人々が経済的な力を有しているという状態でした。
こうして、ミャンマーの人たち、特に主要民族であるビルマ族は、自分たちがずっと暮らしてきた、自分たちが治めるべき土地がイギリスやインドに支配されているという感覚を持つようになったのです。
この感覚は、その後のビルマ族のナショナリズムへとつながっていきます。ビルマ・ナショナリズムの核には、上座部仏教の信仰や長い王朝の歴史、そのもとで育まれたビルマ語の文化などがあります。
しかし、それらに加えて、ビルマ・ナショナリズムには外来者への反発という性質も含まれます。植民地支配を行っていたイギリスだけではなく、植民地時代に経済的に重要な役割を担っていたインド人に対する反発もありました。
1948年に独立したミャンマーでは、主要民族であるビルマ族のナショナリズムを中心とした国づくりがなされました。
ミャンマーの領土の周縁部には、ビルマ族とは異なる多くの少数民族がいましたが、ビルマ民族中心主義のもとで、文化的背景の異なる少数民族は抑圧の対象となりました。当然、それに対する反発が少数民族側から発生し、独立以来、数10年にわたり内戦が続きました。
他方で、ミャンマー政府はインド人など外来者への反発をおさえるため、建前として土着諸民族の連帯を主張しました。つまり、多くの少数民族を抑圧しながらも、それらを土着民族であり、国民であると表向きに認めたのです。
この点でロヒンギャは少数民族の中でも特殊な存在でした。
ロヒンギャの人たちは、ロヒンギャもまた他の少数民族と同様にミャンマーの土着民族であると主張していますが、ミャンマー政府やビルマ・ナショナリズムの立場からは、「土着でない」とみなされてきたからです。ロヒンギャの外見的特徴やムスリムであることも、そうした認識を補強する材料とされてきました。
──では、ロヒンギャの人々はどこにルーツを持つのでしょうか。