「ここは僕らのユートピア」移住者を引きつける相模原市藤野地区の“地域力”
人口7900人の地区に300人の芸術家、戦時中から模索してきた大芸術都市構想
2023.11.10(金)
ここからは、JBpress Premium 限定です。
カンタン登録!続けて記事をお読みください。詳細はこちら
連載の次の記事
東京でも年間194件の「クマ」目撃情報、人身被害も発生している驚きの事実

あわせてお読みください

20ある政令市のなかでも地味な「神奈川県相模原市」が大化けする可能性
市の6割は森林だが、日本最大級の物流拠点やロボット製造集積地の顔も
山田 稔

泉房穂・前明石市長に聞く、子どもの増える国にするには何をすればいいのか?
足りないのはお金ではなく「やる気」、子どもに対する考え方がおかしい日本人
長野 光

今の日本に必要なヘルシーな衰退、徳島県神山町に学ぶ「地域再生のあり方」
神山まるごと高専の開校に湧く神山、過疎地なのにプロジェクトが生まれるワケ
関 瑶子

高齢化率が低下し始めたのはなぜか?久山が実現したヘルシーな人口増の秘密
福岡・博多のお隣なのに懐かしい里山、誰もが住みたい「久山町の研究」(2)
篠原 匡
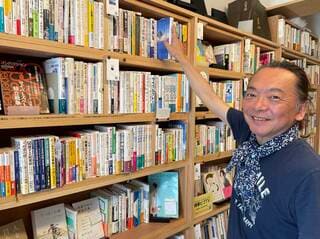
「町の本屋」を復活させる!じり貧の書店業界に構築する新たなエコシステム
連載「だれが本を生かすのか」第2回 安藤哲也の挑戦【後編】
浜田 敬子
本日の新着

「連休で仕事が休みになっちゃって。3000円くらい貸してもらえませんか」大型連休で干からびる派遣高齢者の日常
【令和版おじさんの副業NEO】所持金500円の派遣高齢者が大型連休を乗り切った方法(前編)【JBpressセレクション】
若月 澪子

歯の治療費250万、孫へ贈与が500万…退職金が「蒸発」し、年金が「枯渇」する恐怖
「そこそこの貯蓄」があっても安心できない、年金生活者を襲う想定外の出費
森田 聡子

かつて「野球弱小県」ながら野球熱の高かった新潟県、今は子どもの未来を第一に県球界一丸で取り組む「先進県」に
広尾 晃

「中国が『EUV露光装置』試作機完成」の衝撃…世界の半導体秩序は抜本的に書き換えられてしまうのか?
莫大なカネとヒトをつぎ込んだファーウェイ、中国半導体版「マンハッタン計画」の行方
湯之上 隆
豊かに生きる バックナンバー

西洋の「模倣」から日本独自の「新しき油絵」へ…小出楢重が切り拓いた日本近代洋画の可能性
川岸 徹

姫路城を築いた池田輝政によって近世城郭に整えられた吉田城、一見地味でも何かと面白い要衝の地にある城
西股 総生

大河ドラマ『豊臣兄弟!』第1回で描かれた秀長の本質、兄・秀吉の帰還で動き出す運命──史実の空白をどう埋めた?
真山 知幸

若き曹操を乱世の奸雄にした分岐点、運命が切り替わった理由と混乱期に飛躍する人の共通点
鈴木 博毅

住宅ローンは絶対に繰り上げ返済してはいけない!金利上昇であわてて返済したら大損する理由を合理的に解説
我妻 佳祐

すしざんまい「5億円マグロ」は今年の景気浮揚を「握っている」のか?スーパーの安売りマグロを食べながら考えた
立川 談慶









