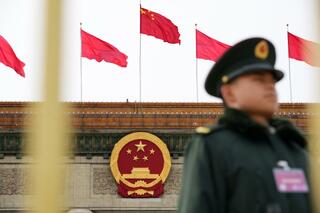「よくある話」がバズった理由
嵩氏:特定の人や団体との間でトラブルになっているように見受けられるからです。
移住に失敗したという人の話の多くは、人間関係によるものです。ただ、人間関係トラブルは基本的に個人間の問題です。問題が表面化するまでの過程においては、どちらかが一方的に何かをした、ということはないと思います。
 嵩和雄(かさみ・かずお)氏 国学院大学観光まちづくり学部 准教授/NPO法人ふるさと回帰支援センター理事。1972年生まれ。東洋大学大学院工学研究科博士後期課程単位取得退学、修士(工学)。2001年に熊本県小国町に移住、(財)阿蘇地域振興デザインセンター、財団法人学びやの里で都市農村交流事業を実践、2009年に東京にUターン。同年よりNPO法人ふるさと回帰センター副事務局長として移住支援に携わり、2021年より国学院大学研究開発推進機構准教授、2022年4月より現職。
嵩和雄(かさみ・かずお)氏 国学院大学観光まちづくり学部 准教授/NPO法人ふるさと回帰支援センター理事。1972年生まれ。東洋大学大学院工学研究科博士後期課程単位取得退学、修士(工学)。2001年に熊本県小国町に移住、(財)阿蘇地域振興デザインセンター、財団法人学びやの里で都市農村交流事業を実践、2009年に東京にUターン。同年よりNPO法人ふるさと回帰センター副事務局長として移住支援に携わり、2021年より国学院大学研究開発推進機構准教授、2022年4月より現職。
お互いのちょっとしたすれ違いや我慢が、臨界点を超えて出てきてしまったのでしょう。
大前提ですが、今回、地元の方々が実際どうだったのかという話はこれまで一切出てきていません。YouTube配信や報道を通して私たちが得られる情報は、片方の当事者の視点ばかりです。この点は留意してみる必要があります。
これまでやってきたことをいきなり否定されたらムカッとくるのが人間です。合理的だとか、費用対効果が高いとか、資本主義のものさしでは測れないものが田舎にはたくさんあります。
そうやっていつのまにか掛け違い、人間関係に悩んだ協力隊員が辞めてしまうというのは「よくある話」です。協力隊に限らず、移住者がすぐに出て行ってしまうということも決して珍しくありません。
――「よくある話」がここまで反響を呼んだのはなぜだと考えられますか。
嵩氏:SNS上の反応を見ると「やっぱり田舎は……」というとらえ方が多いですよね。多くの方が、よくある話だということはわかっているのだと思います。
今回印象的だったのはSNSの効果です。移住してYouTube配信する人も増えてはいますが、ポジティブな内容がほとんどです。今回も最初はそうでした。
逆にネガティブな情報を、素性を明らかにして発信するというのはあまり見られません。当事者の一方の視点だけではどこまでが事実か明確ではありませんが、ここまで赤裸々に語られたということが大きかったのではないでしょうか。
私が心配しているのは、別子山に限らず、過疎に悩む集落の今後のことです。こうしたトラブルが起きた地域では「もう協力隊もよそ者もいらない」というような感じになりかねません。これでは地域にとってマイナスにしかならない。この点は非常に危惧しているところです。
――「ここに移住すると村八分的な扱いを受ける」といったような認識が世間に広まってしまったということでしょうか。
嵩氏:外部の目線もそうですが、一番の懸念は内側の人たちの気持ちです。
外から来た人が次々と出て行ってしまうと、そこで暮らしている人たちは「やっぱりうちの地域はダメか」となってしまいます。その地域に住み続けるということ自体に自信や誇りを失ってしまいます。
それでも、地域はよそ者を受け入れ続ける意識をなくしてはならないと、私は思います。
かつて調査に入った北陸のある集落で、移住者が大麻を栽培して摘発されたということがありました。ですが、その集落の自治会長はポジティブでした。その後も移住者の受け入れをやめず、むしろより熱心に、丁寧に受け入れをするようになったのです。
内部では「もう受け入れはやめよう」といったような反発もあったでしょう。それでも、その自治会長は「移住者はひとくくりで悪く考えない方がいい。その移住者がそうだっただけだ」と言っていました。
結果論かもしれませんが、移住者が増えている地域にはこうした寛容さが共通して見られるような気がします。
――今回の「これだから田舎は」とひとくくりに言ってしまう一部SNS上の言説と対になる考え方のように感じます。
嵩氏:移住者も一人ひとり違うわけです。「過激な村八分にあう地域」というとらえ方がされている今回のケースでも、たまたま今回の移住者と地域とが合わなかった、という要素が大きいとみています。