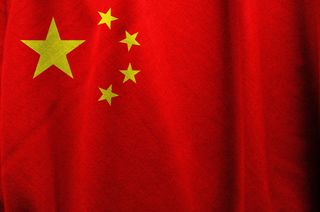だが、人間には一生に一度や二度、大きな分岐点となる出来事や出会いがある。私自身も天安門事件が作家人生の第一歩となったことで、人生の方向性を決定づけられた。100年経てば忘れ去られる歴史的事件であるなら、今一度、100年後の人々に伝えるために、亡命者たちの実情を書き留めておきたいと思う。
亡命先で3派に分裂、乱闘騒ぎまで起こしていた民主化運動のリーダーたち
天安門事件が起きた翌年の1990年、私は海外へ亡命した人々を追って、アメリカとフランスへ取材に行った。アメリカのプリンストン高等研究所には50人近い亡命者が滞在していたが、実際に会ってみて驚いた。学生リーダーと若手作家、中高年の知識人たちが3派に分かれて連日議論に熱中し、天安門事件を引き起こした責任を互いになすり合い、時には乱闘騒ぎまで引き起こしていたのだ。
戸惑う私に忠告してくれたのはノンフィクション作家の劉賓雁(りゅうひんがん)だった。
彼は元光明日報の記者で、文革時代に迫害されて22年間投獄された経験があり、天安門事件では民主化運動を擁護し、学生運動の「黒幕」だとされて亡命を余儀なくされていた。何事にも動じない不屈の精神の持ち主に見受けられた。
「良いことも悪いことも、見たままを率直に書けばよいのですよ」と、彼は言った。趙紫陽(ちょうしよう)総書記の側近で、元体制改革委員会主任だった政治家の陳一諮(ちんいっし)は、「これが中国人の実情です。バラバラなのですよ!」と笑い飛ばし、「だからこそ改革が必要なのです」と力説した。
私は多くの有名無名の亡命者に取材し、翌年、『柴玲の見た夢 天安門の火は消えず』(講談社)を出版した。