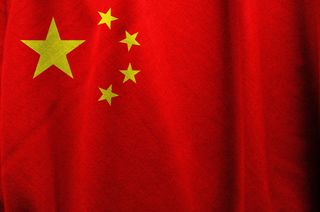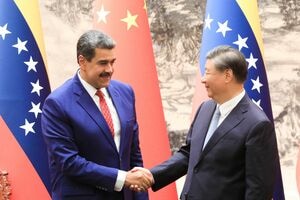1989年6月4日に起きた天安門事件の民主化運動のリーダーたち。左から柴玲、王丹、封従徳、李禄(写真:ロイター/アフロ)
1989年6月4日に起きた天安門事件の民主化運動のリーダーたち。左から柴玲、王丹、封従徳、李禄(写真:ロイター/アフロ)
その後も亡命者たちとの交流は続いた。学生運動のリーダーで「民主の女神」と呼ばれた柴玲(さいれい)は、ボストンの投資会社の経営者と結婚して四児の母になった。柴玲の元夫の封従徳は天安門事件の意味を反芻して哲学に没頭し、世界中の歴史を学び直して、フランスの大学院で博士号を取得した後、改めて中国を見つめ直した。「僕の心の中には今、『理想の中国』がある」と物静かに語った。「現実の中国ではないけどね。人々が平和で幸せに暮らせる夢のような中国だ」と言う。
南京大学の学生で戦略家だった李禄(りろく)は、アメリカのコロンビア大学院を卒業後、投資ファンドを立ち上げて、今は世界的に有名な大富豪の右腕になっている。
「私は祖国を愛している。でも、祖国は私を愛してくれるのか?」
1999年、私は『「天安門」十年の夢』(新潮社)を出版し、亡命者4人の現状を描いた。放送作家の蘇曉康(そぎょうこう)はアメリカへ亡命後、長い米中交渉の末に渡米できた元医師の妻が、交通事故で脳に損傷を受けて一級障害者になったことに衝撃を受け、すべては自分のせいだと後悔して、妻の介護に専念する苦悩の日々を告白した。
新進気鋭のノンフィクション作家の張伯笠(ちょうはくりゅう)は、天安門広場でも巧みな弁舌を振るったが、亡命後は中国系アメリカ人が集うキリスト教会の神父になった。彼の説教を聞いた信徒たちはみな心を動かされ涙するのだという。
ニューヨークで弁護士資格を取得した元学生リーダーは、「お金を稼いで、天安門事件で犠牲になったり、ハンストで植物人間になったりした学生たちの遺族に対し、生活費を送金することが僕の使命なんだ」と、自信に満ちて語った。
カナダ在住の中国人留学生は、ネットにこう書きこんだ。
「私は祖国を愛している。でも、祖国は私を愛してくれるのか?」
天安門事件から33年が過ぎた今、元学生リーダーだった亡命者も60歳を越えた。この先、彼らが晴れて帰国できる日が来るかどうかはわからない。だが1989年の春、北京の抜けるような青空の下で、彼らが熱く語り合った理想と希望がまばゆく輝いていたことだけは間違いない。