上洛するもすぐに下向、一条房家の土佐国内での闘いと対明貿易とのかかわり
「闘う」貴族、土佐一条家の創設と一条房家の実像(2)
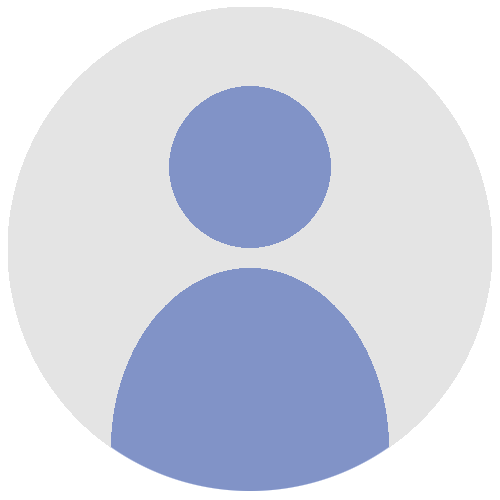
 著者フォロー
フォロー中
著者フォロー
フォロー中
2022.3.24(木)
(中脇 聖:日本史史料研究会研究員)
◉「闘う」貴族、土佐一条家の創設と一条房家の実像(1)(https://jbpress.ismedia.jp/articles/-/69192)
一条房家の上洛と「闘い」
筆者は前回記事で「戦国時代の『闘う』貴族、土佐一条家を創設した一条房家はなぜ、逃げ回っていたのか?」と題して、土佐一条家の初代当主・一条房家の元服までの動向と、元服後の動向を朝廷や公家たち中央政界との交流と姻戚関係について紹介した。今回は、前回記事の続編として房家の上洛と土佐国内での「闘い」や対明貿易とのかかわりなどについて述べてみたい。
一条房家は、これまで触れてきたように、土佐国に「在国」したままで、一度として京の都に上洛(地方から都に赴くこと)したことがなかった。しかし、叔父であり、義兄で摂関一条家の当主であった一条冬良が永正11年(1514)3月に51歳で薨去(こうきょ。三位以上の高位の貴族が死去すること)すると、房家は子息の一人、房通と家臣たち(土佐衆)を伴い2年後の永正13年(1516)12月に上洛するのであった(『後法成寺関白記』永正十三年十二月七日条ほか)。
ちなみに、上洛した房家は同年同月の27日に権大納言に任じられている。常に在京しているわけではない房家の権大納言昇進は異例のことだった。また、房通は冬良生前から男子に恵まれなかった彼(冬良)の養嗣子になることが決められていた。冬良に仕えた中御門宣胤がのちに述べているが、彼は房通の上洛を再三にわたり房家に催促していたらしい(『宣胤卿記』永正十四年四月卅日条)。
しかし、ついに冬良生前には実現していない。房家が冬良の要請に応じなかった理由はわかっていないが、「遺恨」ではないかと宣胤は語っている。冬良薨去という事態に直面した摂関一条家の家政職員(家臣)たちは動揺、混乱してしまう。東坊城和長、中御門宣胤、宣秀父子らが一条家から去って(『宣胤卿記』永正十四年十月十六日条ほか)、他家に仕えるなどした。
それもそのはずで、冬良の後継者に決まっていた房通は一向に上洛せず摂関一条家は完全に機能不全に陥っていたし、ようやく房通を伴って上洛したと思ったのもつかの間、房家は京の都に残ることのないまま再び土佐国へ下向するという。これでは、摂関一条家の先行きに不安をおぼえた家政職員(家臣)たちがいても不思議ではないだろう。
摂関一条家を去る人々がいた一方で、房家・房通の上洛後、子息を家政職員(家臣)に採用を打診する人もいた。松殿忠顕その人である。忠顕は、冬良薨去の混乱に乗じて赴任先の摂津国福原荘(現在の兵庫県神戸市ほか)の年貢を着服するなどの「懈怠」(けたい)を理由に、事実上の解雇を言い渡されてしまう(『宣胤卿記』永正十四年十月五日条)。
解雇された忠顕は、自身の代わりに子息忠豊を推挙し、房家の許可を得て彼の名前の一字を与えられ家豊と名前を改め、家政職員(家臣)となった(『ニ水記』永正十四年五日条ほか)。ここで重要となるのは、摂関一条家の人事を房家が決めているという点である。いくら房通が幼少(当時、9歳)とはいえ本来、当主権限であるはずの人事を房家が決めているということは、一時的な措置だったにせよ摂関一条家の当主として行動していることが注目できる。
さらに、房家は朝廷(天皇)と幕府(将軍家)に参賀し、年頭の挨拶を行うと、翌月には摂関一条家の第(屋敷)で歌会始を催すなどしている(『宣胤卿記』永正十四年正月卅日、同二月七日条)。
房家が土佐国を離れていたのを狙いすますように永正14年(1517)4月、土佐国高岡郡の有力在地領主である津野元実が、房家に属していた射場(戸波)城の福井玄蕃を攻めたのである(『南路志巻二十四』)。一条側は縁の深い在地領主・大平家からの援軍もあり、これを打ち破る(元実敗死)。しかし、一転して津野家の軍勢(津野国泰・中平元忠ら)の激しい抵抗によって一条側も大きな打撃を受けてしまう。
この合戦の報せをうけた房家は、房通の元服と朝廷への拝賀(後柏原天皇への房通元服、叙位の御礼のため)を済ませると、土佐に下向(帰国)するのである。とくに、朝廷への拝賀が房家父・教房の命日(10月5日)だったため、極めて異例のことだったが、それだけ緊急性があると房家が判断したのだろう。
房家が土佐へ下向(帰国)してからの津野家との対立状況には不明なところが多いが、房家が三条西実隆に送った書状(手紙)には「当国忩劇」(土佐国内が混乱している)と記されているので(年月日未詳某【一条房家カ】書状、尊経閣文庫所蔵『春除目抄』紙背文書)、戦乱の火種がくすぶっていたのではないだろうか。
 四万十川最下流にある佐田沈下橋 写真/(公財)高知県観光コンベンション協会
四万十川最下流にある佐田沈下橋 写真/(公財)高知県観光コンベンション協会
















