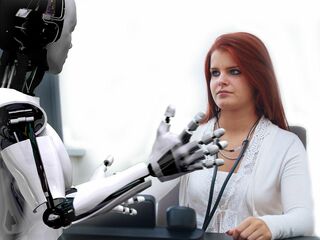遺体の前で慟哭
病院の遺体安置所は少し離れたところにひっそりとあった。
先程の緊迫感が遠い世界の事のように、そこは静まり返っていた。階段の軋む音にさえ慎重になる。ドアを開けると、いきいなり遺体が横たわっていた。見回すと白いタイルの床に四十体ほどの遺体が並べられていた。曇りガラスの窓から幽かな外光が入るだけの冷たい薄暗い部屋は、消毒液のにおいと血のにおいが混ざり合った“死の世界”だった。
遺体はその死の瞬間のままの姿で、冷たいタイルの上で眠っていた。部屋の中に一組の父と息子がいた。
泣いていた。父親が腰をかがめて、横たわる妻の頬を慈しむように撫で続けている。
“死”は取り返しのつかない事なのだ――という想いがあらためて心に突き上げてきた。戦争という殺人は、運命という言葉では片付けられない。
サラエボ五輪のメインスタジアムが犠牲者の埋葬場に
埋葬は早朝か夜中に行われるという。死者の埋葬に集まった人々でさえ標的にされてしまうからだ。かつてオリンピックが開催された時のメインスタジアムは、掘り返されて墓地になっていた。墓地のあちこちに真新しい土盛りが見られる。あのサラエボ冬季オリンピックから10年。平和の祭典のレガシーに今は戦争犠牲者が眠っている。
一人の少女がフェンスの所にポツンと立っていた。声をかける。
「お父さんとお母さんがここにいるの」
少女は小さな声で呟いた。