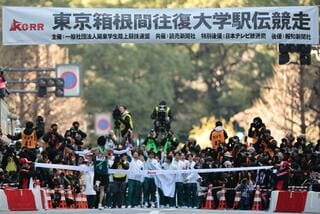『鬼滅の刃』産屋敷耀哉の言葉で紐解く、無惨と産屋敷一族の因果
歴史家が考える鬼滅の刃⑤-2 鬼舞辻無惨の誕生秘話を探る(後編)
2022.2.8(火)
ここからは、JBpress Premium 限定です。
カンタン登録!続けて記事をお読みください。詳細はこちら
あわせてお読みください

『鬼滅の刃』「鬼舞辻無惨は平将門説」は本当か?徹底検証
歴史家が考える鬼滅の刃⑤-1 鬼舞辻無惨の誕生秘話を探る(前編)
乃至 政彦

『鬼滅の刃』十二鬼月の名前の「変化」でわかる、無惨の正体
歴史家が考える鬼滅の刃④-2 十二鬼月のホーリーネーム(後編)
乃至 政彦

『鬼滅の刃』十二鬼月の名前に秘められた、鬼舞辻無惨の真意
歴史家が考える鬼滅の刃④-1 十二鬼月のホーリーネーム(前編)
乃至 政彦

漫画の王道を覆す『鬼滅の刃』下弦の鬼を完全粛清した無惨の真意
歴史家が考える鬼滅の刃③鬼舞辻無惨のパワハラ会議は本当か?
乃至 政彦

『鬼滅の刃』鬼だけでない、鬼殺隊存亡の危機とは
歴史家が考える鬼滅の刃②-2 鬼殺隊の創設と改革に関する仮説(後)
乃至 政彦
本日の新着
豊かに生きる バックナンバー

シチリアワインはイタリアワイン? 変革者「ドンナフガータ」のはじまりの地へ
佐々木 ケイ

顔がない石仏、木の根が絡みつく仏頭…かつての黄金都市「アユタヤ」を象徴する文化財に修復は必要か?
髙城 千昭

哲学者・西周が覚悟の脱藩を決めた黒船の衝撃、洋学修得へのまい進と、単なる知的好奇心ではなかった転身の本質
町田 明広

『ばけばけ』小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)の後半生、セツとの出会い、意思疎通はヘルン語、当時は珍しい帰化
鷹橋 忍

日本と韓国が「ともに生きる」ために必要なものとは?日本の敗戦から80年間の日韓関係をアートで表現する意義
川岸 徹

生産終了が迫るアルピーヌ A110と賢者の選択
大谷 達也