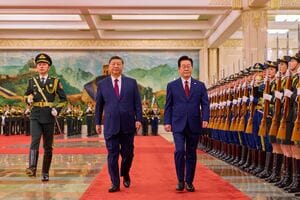被害者や遺族はなぜ加害者とやり取りするのか?
藤井:僕が取材したケースでは、1回だけ心情等伝達制度を利用する(受刑者と1往復だけ言葉を交換する)人がほとんどでした。
理由は「諦め」です。謝罪の言葉が返ってきたとしても、行間から加害者の本心や無関心を被害者や遺族は感じ取ります。それで「しょせん、こんなものか」という感想を持つようです。被害者にとっては、ある意味「心の整理」になるのでしょうが、それは諦めに似たネガティブな気持ちのようです。
──被害者や遺族の方が、この制度を使って加害者とやり取りしたいと思う動機はいったい何なのだろうかとこの本を読みながら次第に疑問に思いました。
藤井:被害者や遺族は、加害者が変化しているかどうかを見極めたいのだと思います。もちろんどんな言葉が返ってきても、被害者の側は許せないという気持ちは消えないし、それが前提になっています。それでも何年も経つ中で、加害者の心境にも変化が出ているかもしれず、それを見たいという思いがある。
実際にはごく稀なケースなのですが、刑務所の中で本当に深く反省する受刑者もいます。私がかつて『贖罪』という本を書く過程で文通したある受刑者は、刑務所の中で膨大に本を読み、他の受刑者とも話をする人でした。彼は、次第に自分がしてしまったことを理解して、強烈なショックを覚えていました。
──心情等伝達制度を利用して、加害者と被害者・遺族がやり取りをする中で、裁判の中での加害者の発言が加害者の真意ではなく、弁護士の誘導による回答だと分かってくることがあると書かれています。

藤井:加害者は裁判中に、少しでも自分に有利に働くように代理人弁護士に相談します。弁護士が加害者にどのような指示を出していたのか、そのあたりが心情等伝達制度を通したやり取りの中で半ば偶発的に明らかになります。
もちろん、弁護士の誘導が後から明らかになっても、被害者側が何かできるわけではありません。それでも、何でもやる刑事弁護士がいるんだということがよく分かるエピソードです。
こうした代理人弁護士による過剰な誘導はこれまでもある程度は問題になってきましたが、メディアは大きく取り上げてきませんでした。そういうものだという認識がむしろ一般的だと思います。この本にも書きましたけれど、中にはAIを使って謝罪文を作るような弁護士もいるのです。
藤井 誠二 (ふじい・せいじ)
ノンフィクションライター
1965年愛知県生まれ。取材テーマの主軸の一つに「少年犯罪」を置いて長年にわたって取材・執筆活動をしている。愛知淑徳大学非常勤講師。テレビやラジオ等でもコメンテーターやコーディネーターを務めてきた。著書に『贖罪』(集英社新書)、『沖縄アンダーグラウンド』(集英社)、『誰も書かなかった 玉城デニーの青春』(光文社)、『人を殺してみたかった』(双葉文庫)、『少年に奪われた人生』(朝日新聞出版)、『殺された側の論理』『アフター・ザ・クライム』(以上、講談社)、『黙秘の壁』(潮出版社)、『死刑のある国ニッポン』(森達也氏との共著・河出文庫)、『ソウル・サーチン』(新里堅進氏らとの共著・リイド社)など多数。
長野光(ながの・ひかる)
ビデオジャーナリスト
高校卒業後に渡米、米ラトガーズ大学卒業(専攻は美術)。芸術家のアシスタント、テレビ番組制作会社、日経BPニューヨーク支局記者、市場調査会社などを経て独立。JBpressの動画シリーズ「Straight Talk」リポーター。YouTubeチャンネル「著者が語る」を運営し、本の著者にインタビューしている。