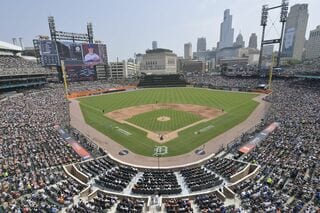甲子園システムの光と影
高校野球が他の高校スポーツと比べて、比較にならないほどの高い注目度を集めてきたのは、春、夏の休み期間に甲子園で集中開催してきたことによるメディア露出効果が否定できない。
私学にとって甲子園出場の宣伝効果は大きく、それゆえに部の強化に大金を投じてきた面も否めない。そして、大会を大々的に報じるメディアにとっても、高校野球はキラー・コンテンツだ。
負けたら終わりのトーナメント方式で、一つのプレーに球児が歓喜する文字通りの「筋書のないドラマ」が展開され、多くのファンを魅了してきた。このため、新聞、テレビなどのメディアは取材班を組み、現地から熱戦の様子を映像や記事で配信。ビジネス機会を得るとともに、高校野球のブランドイメージも確立されてきた。
 トーナメント方式だからこそ甲子園では様々なドラマが生まれる。写真は第107回全国高校野球選手権大会で優勝し、大喜びする沖縄尚学ナイン(写真:スポーツ報知/アフロ)
トーナメント方式だからこそ甲子園では様々なドラマが生まれる。写真は第107回全国高校野球選手権大会で優勝し、大喜びする沖縄尚学ナイン(写真:スポーツ報知/アフロ)
一方で、投手の肩・肘への酷使は昔から指摘され、近年の猛暑開催には批判の声も高まってきた。
野球は、リーグ戦で実施したほうが、選手層などのチームの総合力が、実力通りに評価されやすい。
多くの選手を集めた強豪校が優位になったとしても、試合間隔が開けば、けがのリスクは軽減される。「夏に炎天下の甲子園での集中開催」にこだわらず、数カ月のスパンで週末の午前、夕方開催のリーグ戦に移行すれば、学校の授業への影響もなく、熱中症リスクも大幅に軽減されるだろう。
しかし、「時期を分散したリーグ戦」「甲子園以外での開催」では、おそらくこれまでのような高校野球の盛り上がりにはならないだろう。
「夏に炎天下の甲子園での集中開催」は、私学を中心とした加盟校にとっても、キラー・コンテンツとして報道を続けたいメディアにとっても、そして高校野球の文化を継承してきた日本高野連にとっても、切り込まれたくない“聖域”になっているはずだ。
しかし、この点と向き合わなければ議論は深まらない。