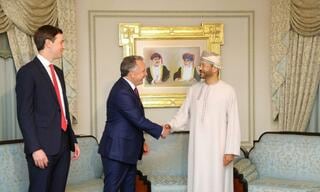写真:baking/イメージマート
写真:baking/イメージマート
今日では冬の定番として定着した「肉まん」だが、その普及の陰には、近代日本が抱えた「栄養不足」という構造的課題があった。国を挙げた栄養改善が急務となる中、1910年代、学界・政府・畜産業界が一体となって豚肉食の普及に取り組んだ。新聞でのレシピ公開は読者の反響を呼び、豚肉料理の認知は一気に広まった。その象徴となったのが中国料理を応用した肉まんである。肉まんは単なる軽食ではなく、近代化の象徴として社会に浸透していった。(JBpress編集部)
(岩間一弘、東洋史学者)
※本稿は『中華料理と日本人 帝国主義から懐かしの味への100年史』(岩間一弘著、中央公論新社)より一部抜粋・再編集したものです。
肉まんは、小麦粉・酵母・ベーキングパウダーなどをこねて発酵させて膨らませた生地で、豚ひき肉やタマネギを混ぜた餡を包み、蒸した饅頭である。
それは、中国では「包子(バオズ)」「肉包(ロウバオ)」、日本では「肉まん」「豚まん」「中華まん」、韓国では「チンパン(찐빵、蒸しパン)」などと呼ばれ、屋台、専門店、レストラン、コンビニ、スーパーなどで売られ、日常的に食べられている。
日本人の栄養改善のために行われた「豚肉食の啓蒙」
日本において肉まんが普及するきっかけになったのは、国民の栄養状況を改善するために、学者、畜産業界、政府が一体となって、豚肉食を宣伝したからであった。
肉まんは、18世紀から受容されていたが、栄養キャンペーンという近代的なプロジェクトの開始とともに庶民に広く普及し始めた。
日本における豚肉食の歴史を振り返っておこう。
鹿児島では、16世紀以前から養豚が行われていた。1609年に薩摩藩が琉球に進攻した際にも豚を持ち帰り、江戸時代には養豚が発展した。
19世紀後半でも、全国の豚の3分の2近くを鹿児島県が産出しており、日本本土には鹿児島県以外に目立った豚肉の産地がなかった。
明治期に入ると、国が養豚を奨励し、1871年には養豚が一時流行した。
また、1872年の明治天皇による肉食奨励によって、牛肉食が流行し、それが豚肉食の流行にもつながった。
しかし、それでも日本国内における豚肉の需要が大きく増加することはなかった。
日清・日露戦争によって豚肉の価格が高騰し、一時的に養豚業が活況を呈したが、ほとんどが投機的な事業に終わり、豚肉食の本格的な普及にはつながらなかった。
1912年頃の日本人一人あたりの牛・羊・豚・馬肉の合計の年間平均消費量は約0.77キログラムで、これは世界最低水準に近かった。
肉の消費量が多いオーストラリア(約125キロ)やアメリカ合衆国(約68キロ)などに比べると、わずか100分の1ほどしかなかった。
こうしたなかで、国民の栄養、健康状況を改善するための啓蒙・教育活動として、豚肉食の普及が提唱された。